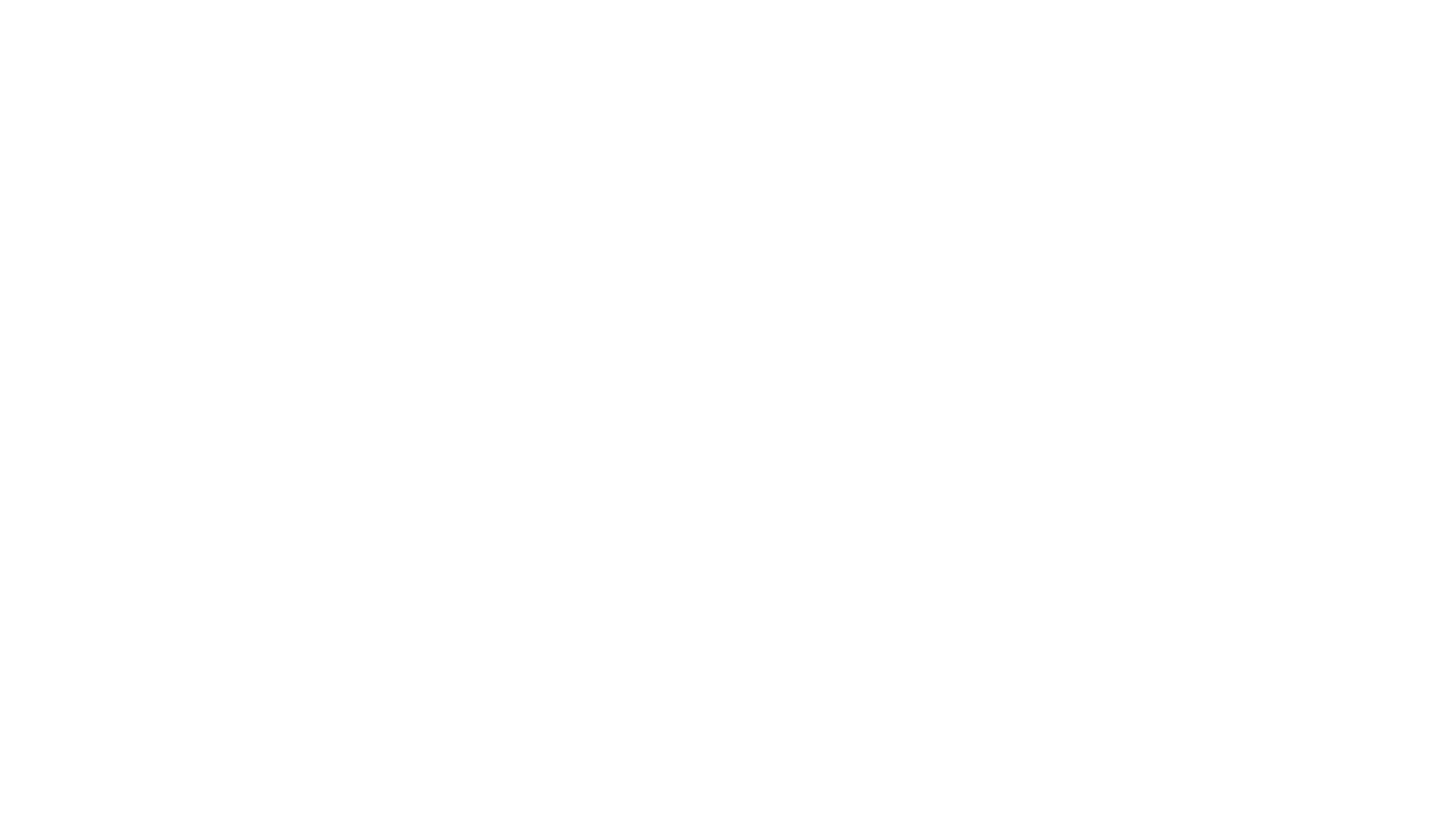突如として舞い込んだ「長男結婚」の報。言うまでもなく、それは我が家にとって大大大事件でした。
とはいえ、そのとき私は小学4年の小僧。「結婚」が何なのかなんて分かっちゃいません。
しかし、それでも「兄が家を出て行く」ということだけはなんとなく理解していたのです。
本人には口が裂けても言えませんが、当時はそれが本当に嫌で嫌で仕方ありませんでした。
音楽がどうこうではなく、彼は親以上に私を可愛がってくれていた自慢の兄だったからです。
迎えた結婚式。入場曲は『JUPITER』でした。
今思えば「どう考えても結婚式で流す曲じゃないだろ」なその選曲。
しかし、当時歌詞の意味など知る由もなかった私にとって「ただただ綺麗な曲」という認識であったその名バラードは私だけでなく親戚一同にも違和感を与えることなく、祝福の場を華やかに盛り立ててくれていました。
神秘的な空気に包まれた会場を緊張気味の笑顔で歩く二人がとても幸せそうで、寂しいと同時にとても嬉しくなったことを覚えています。
それからというもの、兄はあまり家に帰って来なくなりました。
新居がうちから遠いこともあってか、いつまでも残りの荷物を取りに来ず、そのくせBUCK-TICKのCDやビデオだけはしっかりと持って行きやがったので、必然的に私はその音楽に触れる手段を失ってしまうのです。
大袈裟だと笑われそうだけど、一日がとてもつまらなかった。
天井に10年以上貼ってあった大きなBUCK-TICKが消えたせいで、眠るときに嫌でも5人と目が合うあの妙な緊迫タイムもなくなりました。
そして、あれ程までに毎日稼働していたラジカセは見る見る埃を被り、まるで構ってもらえないペットの様な顔でこちらを見るのです。
ある日、そんな退屈に耐えかねた私は小さな目標を立てることになります。
それは、「お小遣いを貯めて、バクチクのCDを買おう」というものでした。
駄菓子も絵本も我慢して、微々たるお小遣いをこっそり貯金箱に放り込む生活をスタートさせたのです。
なんだか悪いことをしているみたいで、結局最後まで親には言えませんでしたが。
当時のCDは、900円ちょっとで2曲入り。今のものと比べて、作り自体も大変質素なもの。
しかし、私はディスクを囲う骨の様な白いプラスチックに触れたときの独特なパキパキ感が大好きでした。
私にとって、あの頃のCDはキラキラ光る宝物で、その価値は自分で稼いだお金で買える様になった今でもそう大きく変わりません。
そして、貯金開始から数ヶ月後。その貯金額は、ようやく目標であった千円を突破しました。
親が買い物に行っている隙を見計らい、学習机の裏に隠した貯金箱から何度もお金を出しては金額を確認。「貯まってる!」とテンションマックスな私は翌日学校から帰ると、貯金箱の中身を全て財布に詰め込み、一目散に外へと駆け出します。向かう先は当然CD屋さんです。
今はもうなくなってしまった駅前通りの小さなCD屋。兄に連れられて初めて入ったあの頃から、そこは宝の山でした。
小銭だらけの千円を収めた重たい財布片手にソワソワしながら店内へ入ると、壁にはポスターが所狭しと貼られており、そのなかにはBUCK-TICKとLUNA SEAの姿もありました。
見たことのないアーティストのポスターを見つける度に「これはなんていう人たちなんだろう」と、足を止めじっと凝視。
と、ここで、いつまでも店内をウロウロしている小学生の私に店員のおじさんが話しかけてきます。
おじさん「何か探してるの?」
私「バクチクのCDはどこにありますか?」
おじさんは少し驚いた顔をしたまま、屈んでこう言いました。
「あっちだよ。おつかい頼まれたの?」
「いや、僕が欲しいから買いに来たんです…」
私が小さくそう返すと、おじさんは笑いながらお店の奥へと案内してくれました。
当時、BUCK-TICKは世を席捲する大人気バンドでした(今もそうだけど)。
なもので、小さなお店ながらもそこには立派な「BUCK-TICKコーナー」が。
そこで、私はあの頃イヤって程見てきたジャケットたちと久々の再会を果たすのです。
「あ。あれはあの曲が入ってるやつだ」
「あの曲はあそこが格好良いんだよなぁ」
頭のなかでそんなことを呟きながら、ひとつひとつを手にとってマジマジと見つめます。
お客が私ひとりしかいない狭い店内におそらく一時間は滞在していたでしょう。
33年生きてきた人生のなかで「あんなに充実していた時間が他にあったかな?」と思える程、ハイパーワクワクしながらコーナーを眺めていたとき、私は少し背の高い展示台の一番上に見覚えのないものを発見します。思わず「あ!」と漏れる声。
そして、目線の先にあるそれをおじさんのところまで持っていき、こう尋ねるのです。
私「これ。バクチクですか?」
おじさん「そうだよ」
「見たことないです」
「一番新しく出たCDだよ」
「へぇー…」
悩みに悩んだ末、私はこれまで必死に貯めてきたジャリ銭を会計台へ広げました。
こうして、根こそぎ奪われた貯金箱の中身と引き換えに、少年は一枚のCDを手に入れるのです。
それは、1996年に発売された『キャンディ』という作品。
私が生まれて初めて買ったCDでした。
会計を済ませ、おじさんにお礼を言い、店を一歩出る。
すると、そこで私は原因不明のドキドキに襲われます。
何を思い立ったか、お店の袋に入ったCDを取り出し、ビニールは剥がさないまま、駄菓子屋にはまず売っていないその超危険な『キャンディ』を手に家までの道を突っ走るのです。
うだる様な暑い暑い帰り道を抜け、玄関まで辿り着くと即座に服の中へCDを隠す!そして、音を立てずに家の奥までゆっくりと歩きます。
そう、私にとって「BUCK-TICK」は秘密兵器であり、当時出来た最大限の「ワル行為」でした。
「聴くならこっそり」が鉄則であり、「買ったことがバレたら親に何を言われるか分かったもんじゃない」と、その秘密が暴かれることを心底恐れていたのです。
兄の幼稚っぷりをそのまま引き継いだ末っ子こと私は、その日家に帰って一日が終わるまでの数時間、ヒヤヒヤが止まりませんでした。
家族で食卓を囲み夕食を。
とにかくCDが聴きたくて仕方ない。
次男と父母の会話すらも右から左。
いや、むしろ右から入ってきさえもしない。
ご飯を口に運びながら、遠くにポツンとあるラジカセをじっと見つめる。
見ていることがバレると怖いから、ときどき目線を外す。
味のしない夕食が終わる。
お風呂に入る。
そして、家族が眠りにつく。
よし…今だ…
並じゃない胸の高鳴りは、まだ成長しきっていない体を物理的に揺らすほど激しいものでした。
「バクチクを聴く=ワル」という方程式がいつ出来たものなのかは知りませんが、今になっても「それはあながち間違っちゃいない」と思う私がいます。なんとなく分かるでしょ。この感じ(求ム同調)。
寝静まった家族を跨ぎ、そーっとCDラジカセを浴室まで運ぶミッション。
昔のラジカセは大きいし重たいし部屋は暗いしで、物音を立てずに移動させるのは至難のわざでした。
様々な障害物を越えて抜き足差し足、しずしずと浴室に繋がる台所へ。
コンロ台についているコンセントへラジカセのアダプターを差し込み、限界までコードを引っ張って本体を浴室へ逃がす。そして、ケーブルの通る隙間だけをあけ、浴室のドアをそっとクローズ。
まるで殺人犯がアリバイ工作を施す様な心境で「はぁ…」とため息ひとつ、小さなCDをトレイにのせ、音量を極限まで左へ絞り、あの日以来触れることのなかった再生ボタンへそっと圧力をかけるのです。
CDの回るキュルキュル音にさえも、「おい!静かにしろ!」と言いたくなる静かな夜。
黄緑色のディスプレイに「0:01」と表示された瞬間、聴いたことのないBUCK-TICKの歌が始まりました。
兄との約束を破った気がしてちょっと複雑な気持ちでしたが、「んなこと知るか」とばかり、外から入る電灯の明かりを頼りに歌詞カードを目で追い、何度も小声で口ずさみます。
ときどき「兄ちゃんは多分ここでかっけぇ!って言うんだろうなぁ」とか「でも、本当にかっこいいのはここだな」なんてことをひとり思いながら。
リピートを重ねる度、致死量のスリルに震える心臓が徐々に穏やかになっていくのを感じました。
しかし、再生が5周目に差し掛かった頃、ここで「兄の結婚」以上の大事件が起こります。
少し離れた場所から鈍い物音が聞こえてきたのです。
ドンドンットントンッ
それは、台所へと続くドアが開く音でした。
薄く開いた浴室のドアからそっと覗くと、そこには母の形をした影が一歩また一歩とこちらへ近付いてくるのが見えます。
そして、まだ距離のあるその場所から響いた「なにしてるの?」の声に、私は人類史上最大級の危機を覚えるのです(まじ大袈裟じゃない)。
暗い浴室のなか、急いで音楽を止めようとしたそのとき、あろうことか水滴に体を滑らせてしまい、音量ボタンを逆にひねった上、その横にあるバスボリューム(低音調節)まで同じ方向にドカンとひねってしまった私は、樋口ブラザーズのグルーヴを最大限に主張させた『キャンディ』を母にお見舞いする事態に。
もうこうなったら後がねぇ。埼玉に神などいねぇ。
逃げ出す道などあるわけもなく、私と母の間にある唯一の防具であったドアが向こう側から開け放たれます。
もう…
終わりや…
私は堪忍して俯く。
それから1秒、5秒、10秒のときが過ぎました。
しかし、目の前に見える母の足の方角からは、何の声も聞こえてきません。
なんせ怒ると超おっかない人です。今は静かにしているだけで、油断した私が顔を上げる瞬間を今か今かと待っているのかもしれない。
恐怖値の針が振り切れながらも、「なんで怒鳴り声がしないんだろう…」と、その謎に負けてしまった私は恐る恐る顔を上げてみました。
…あれ
なんと、そこには口を手で抑えたままクッククックと笑っている母の姿。
急にすべてが恥ずかしくなった私は急いで停止ボタンを押し、ラジカセをそこに残したまま布団へと戻りました。無論、無言で。
笑ってはいたけれど、何か言ったら怒られそうな気がしたからね。
しかし、そんな私の心配をよそにその日は特にそれについて触れられることはなく、翌朝食パンを食べながら「なんか昨日の夜うるさくなかった?」と尋ねる次男のデリカシーゼロな発言にも母は「そう?」としらを切っていました。それが逆に怖かった。
それからというもの、「BUCK-TICK」が決して「ワル」でないことを知った私は、白昼堂々日課の様にBUCK-TICKを聴きました。もちろん兄の様に爆音ではなく、耳に優しい音量で。
そんな私が中学生になろうとした頃、兄に娘が生まれました。
親に孫を見せるべくちょこちょこ家に帰って来るようになった兄。
彼は私の顔を見るなり、あの頃よりもずっと性能の良いビデオデッキへBUCK-TICKの最新ビデオを入れ、あの頃と変わらないテンションでああだこうだと喚きます。
本人には未だに言っていませんが、実は私もそのビデオを持っていました。でも、黙っていたのです。
私がもし国語のテストを作成する人間だったとしたら、「このとき筆者は何故黙っていたのかを20文字以内で答えなさい」という問いを設けたことでしょう。
そして、この問題を読んでいる皆様の正解率が100%であることをなんとなく感じています。
久々に兄と観るBUCK-TICK。
そりゃもうやはり文句なしにかっけぇ!そして、何より一人で観るよりもずっと楽しい。
兄の必殺技である「ここがいいんだ光線」に「へぇー」と相槌を打ちながら画面を見つめれば、すぐ隣にはそんな二人に冷たい視線を送る次男の姿が。
どうしたもんか。ここまで成長しない三兄弟が他にいるだろうか。
それからしばらくしたある日、兄がBUCK-TICKのチケットを2枚持って私のもとへやってきました。
彼は誇らしげにその内の1枚を手渡し、「誕生日近いからライヴに連れてってやるよ」と言いました。
更に「ライヴではこのアルバムの曲やるから」と、当時の最新アルバムを録音したカセットテープをくれたのです。
「ありがとう」と受け取ったものの、やはりこれまた私が既に持っているCD。
しかし、ライヴ当日まではずっと兄から貰ったテープの方で曲を聴いていました。
勘違いだとは思いますが、CDよりずっと荒い音質のそれから聴こえる歌が、いつもより格好良く聴こえたからです。
そして迎えたライヴ当日。兄の車で大宮ソニックシティへ。
行きの運転中に流れる音楽は、言うまでもなくBUCK-TICK一色でした。更に言うまでもなく超爆音の。
とはいえ、私が住んでいたのは与野市(現さいたま市)です。大宮市(以下同文)なんて歩いても行ける距離ですから、数曲も聴かぬ内に会場に到着してしまいます。
あの時間があと30分続いていたら、私の鼓膜は開演を前に死亡していたことかと思いますので、「LOVE SAITAMA」の念はいつまでも拭えません。
重厚なドアを開け、初めて目にした音楽ホール。
綺麗な椅子の並びと広いステージ、そして高くから下ろされた真っ赤な幕に見惚れる私。
決して「良席」とは言えない席につき、興奮気味に何かを語る兄の声を無意識に無視しながら、まだ開かないその幕をじっと見つめました。
そしてここで、私はふとこんな質問を漏らすのです。
「今からそこに、BUCK-TICKが来るんだよね?」
兄は笑っていました。その理由はなんとなく分かります。
でも、そう思わずには、聞かずにはいられなかったのです。
今まで画面の中、ラジカセの中でしか生きていなかったBUCK-TICKが、まもなく目の前に現れる。有り得ない話でした。
もうこの時点でファン歴12年。まだ開演前だというのに興奮はピークへ。
ありのままを言えば、飲んでいたミルクティーを吐きそうなくらいに緊張していました。
そして、場内は暗転。
何千もの人たちが瞬時に立ちあがり、耳を裂く程に大きく湧いた歓声。
その瞬間に感じた言い様のない高揚は、あの日CD屋さんで『キャンディ』を見付けたときとは比べ物にならないものでした。
そこから先のことはほとんど覚えていません。
でも、一曲一曲イントロが鳴る度に兄と顔を見合わせ「うわーっ!!」と声をあげていたことだけはよく覚えています(すごく恥ずかしい)。
夢の様な時間でした。
というより、私にとってそれは紛れもなく「夢」そのものでした。
帰りの車。
流れるのは、やっぱりBUCK-TICK。
ライヴを振り返りたいがために超遠回りをしながら、二人を乗せた車は長い夜の道を行きました。
今日観た曲を再度カーステレオで聴き、「ここで今井がこういう動きしたの観た?」「観た!」なんて馬鹿みたいに盛り上がったものです(死ぬほど恥ずかしい)。
行きは夢の予習。
帰りの車の中は、夢の続き。
本当に楽しくて嬉しくて、その日はまったく眠れませんでした。
BUCK-TICKのライヴには、その後も兄と何度も参加しました。毎年一回ずつ。12月の終わりに。
何度行っても緊張し、何度行っても褪せない感動をくれるBUCK-TICKに「これ以上なんてない」と幾度も思わされたものです。
でも、それから数年後。
19になった私は就職のために親元を離れ、「なんとなく面倒だから」という理由で実家にまったく帰らなくなりました。
当然長男と接する機会もなく、実はもうかれこれ15年近く彼とは顔を合わせていません。
慣れない仕事に疲れ切っていた私は、「あいつ元気にしてるの?って、お兄ちゃんが言ってたよ」という母からのメールにも「そうなんだ」と一言返信するだけでした。
新作は絶えず追い続けながらも、BUCK-TICKのライヴには足を運ばなくなった私。
仕事は忙しいし、休みは平日だし、彼女とデートしたいし、終業後なんてもう夜中だから。
そうは思いつつも、出る音源出る音源を耳にしては、「何をどう考えたらこんなメロディーを無限に思いつくんだろう?」と、私が知り得る「本物の唯一無二」に毎度打ちひしがれるのでした。
そして、BUCK-TICKの新しいCDを家まで持ち帰るときには決まって、『キャンディ』を抱えながら汗だくで走ったあの日を思い出すのです。
ずっと離れてしまっていたことで再び偶像化してしまったBUCK-TICKに、そしてきっと同じ会場で飛び跳ねているであろう兄に会うために、私は近々彼らのライヴに行きたいと思っています。チケットの競争率すごそうだなぁ…
おしまい