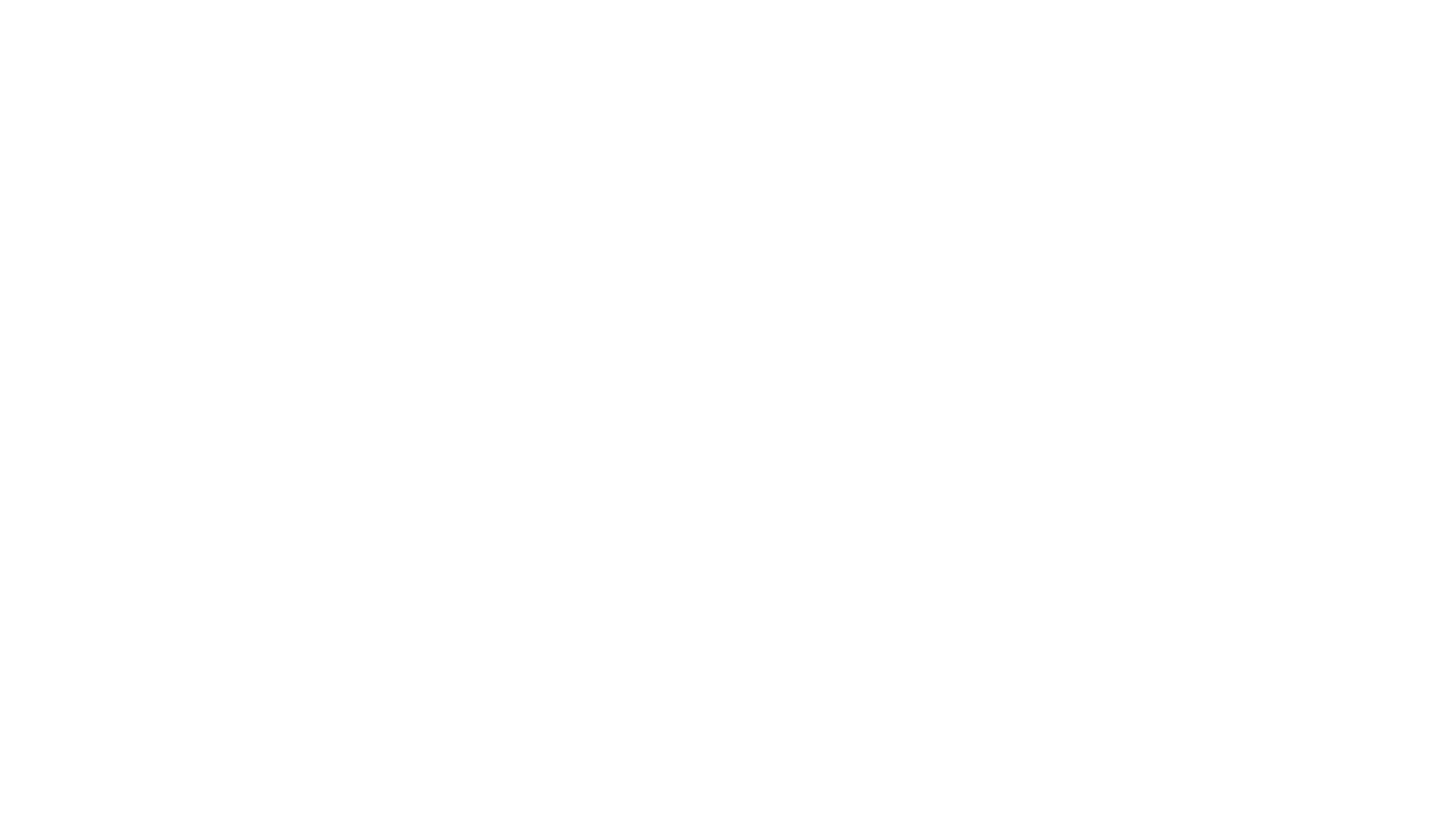「そこに在るだけで美しいものは、そこに在る”だけ”ではないからこそ、美しく在り続けられる」
つい先日、部屋を整理していたときにヒョッコリ顔を出した『ロケット』のシングルCD。
なにげなく手に取り、コンポに入れ、じっくりと思い出の曲に触れてみたとき、ふと浮かんだ想いがそれでした。
リリースされた当時(2000年)、通っていた中学で禁止されていた「携帯電話」と「音楽プレイヤー」の持ち歩き。
「校則なんて知ったこっちゃねぇ」系男子ではなかった私ですが、家から学校までの通学路が遠かったため、暇つぶしとしてMDウォークマンだけはこそこそ鞄に忍ばせていました。
帰り道、みんなから離れた途端に急いでボタンに触れ、『ロケット』の再生を。
それが習慣になる程、暇さえあればずっと聴いていた大好きな曲でした。
あれからもう十数年か。
久々に再生したCDからはあの頃と何も変わらない音と声が流れ、楽曲の描く世界とはまるで関係のない通学路のこと、その頃学校で起こっていた問題やブーム、何もしていないのに何故か私にだけ吠える近所の犬のことなんかを思い出すのです。
なんだか不思議な気持ちに陥りながら「もう掃除はここまでにしよう」と手を止め、久方ぶりに歌詞カードを開きました。そして、ぼんやりとこんなことを思ったのです。
「久しぶりにプラトゥリ観たいなぁ…」
私が彼らのライヴを最後に観たのは2001年のSWEET TRANCE。代々木第一体育館の5列目でした。
あんなに近くでアーティストを観ることなんてそうそうないですし、後に映像化されたDVDにバッチリ映っているしで「なんともマァ」な思い出が詰まった公演。
それまでにもおそらく20回以上はプラを観てきたかと思いますが、そのどれもがイベントライヴであり、彼らを一番の目当てとして参加したものは一つとしてありませんでした。更に言うと、作品的には『トロイメライ』以降の楽曲をほとんど知りません。我、生粋のピエラーだったもので。へい。
でも、本当に好きだったんだ。
誰に言うわけでもないけど、ずっと聴いていた。
けど、理由もなく気付けばそこから離れていて、つい先日まで彼らの存在を「実体」として体感することがなかったのも事実です。
思い立ったが何とやらが座右の銘である私は、「もうそろそろ次の曲いきません?」とコンポのぼやきが聞こえるまでにリピートさせつづけた『ロケット』を横耳に(日本語)、オフィシャルサイトで現在のライヴ情報を調べました。
すると、なにやら一際オゾマシイ公演タイトルがギラついているではありませんか。
2015年5月23日 男子限定LIVE『Boys Don’t Cry』
失礼ながら、今まで私が目にしてきた男性限定ライヴの告知中、最もそれが似合わなそうなバンドだったものですから、公演スタイルへの好奇心半分・単純にライヴが観たいという欲求半分で近所のファミリーマートへ駆け出し、チケットを購入しました。
その翌日にチケットがソールドアウトしたとの知らせを聞いたので、この「ギリギリ」はきっと私を15年待ってくれていたんだと思うことにして、待ちつ待たれつなその日を楽しみにしていました。
そして、ついに当日。
会場に入ってみると既に満員御礼な渋谷GUILTY。
横長のステージで、バックにはステージ幅に合わせたスクリーン。
物々しい雰囲気と言うよりも、これから起こる新しい出来事への高揚が客席に溢れていました。
でね、開演までの時間をひとり、どう過ごしていたかというと、ここぞとばかりに聞き耳を立てたよ。
私とは違って、これまでのPlastic Treeをずっと応援し続けてきた彼らは一体どんなことを思ってここに来たのだろうと、ただそれが知りたくて。
耳立て30秒。
思わず頬が緩んでしまった。
というのも、彼らはこの世にはそれしか娯楽がないかの如く、Plastic Treeの話しかしていないんだ。
何の曲が聴きたいとか、あの曲のここが好きとか、この曲やってくれたら凄そうとか、こんなに楽しみなライヴ他にないとか、緊張して吐きそうとか、とにかく落ち着きのなさが尋常じゃなかった。
ちょっと余所行きな心構えで浮つくご近所さんの声に好奇心をくすぐられながら、私はじっとステージを眺める。
すると、談笑の声も鳴りやまないままに、暗転。
「男子限定とは言ってもそこはプラスティックトゥリーだ。他の男限定よりいくらかは大人しいだろ…」という予感を一瞬で消し去る怒号の様な歓声と、一斉に前へ押し寄せる高身長の波。
一気に身の周りが涼しくなり、「やっぱり私みたいにじっと観ているタイプの人もいるんだな」と安堵しつつ、周りを見渡すとあれまぁここは最後列。
気付けば、その列以外の猛者どもがこぞってステージに吸引され、声をあげまくっているという大惨事でした。
竜太朗さんが初っ端のMCで笑うしかないといった表情でこぼした「想像以上でした。」の言葉。
その洗礼を暗転から10秒もしない内に感じ取った私は驚愕の丘で、立ち尽くすー
ステージに現れるなり、その惨状を見て大笑いしているアキラさんと、平静を装おうとするも微笑みを隠しきれない正さん(ケンケンさんは全く見えなかった。178あるのに。なんせ大勢の手がステージを覆いやがって)。
そして、竜太朗さんが片手をあげて現れると聴覚をやられる程の歓声がドワァァアッとこだまし、轟音に包まれる中、言葉もなく、まどろみの世界へ『Thirteenth Friday』。
熱気に溢れた場内をぐにゃりねじ伏せるサウンドに海底から空を見上げた様な景色がゆらゆらとスクリーン一杯に広がり、さっきまでの馬鹿騒ぎが嘘だったかの様、その音色と気だるい歌唱に身を任せる男たちの後ろ姿が妙に愛らしい。
そうそう。私は事の始まりから終わりの瞬間に至るまで、ずっと同じことを思っていたんだった。
ここに集まった男たちはやっぱり確実に文系で、下手したら女性よりも遥かにロマンチックな種族だってこと。
普段ライヴ会場で見ている女性たちのヘドバンや折りたたみ、拍に合わせたオイ!オイ!のコールや振り。彼女たちが見せてくれるそれらの完成度たるやプロそのもの。
でも、この日の、特に序盤に見て取れた男たちのそれは、不器用さに溢れていて、慣れないながらも男限定らしいライヴをバンドに見せつけてやろうという熱い想いがヒシヒシと伝わってきたのです。
これは「不格好」という意味ではなくて、男特有の「出来ないかもしれないけど、思いのままに感情を爆発させてみたい。メンバーを喜ばせる為にもとりあえずやってみよう」という不器用なりの真っ直ぐな愛情表現。それが本当に温かかった。
こんなときだからこその「多少の無理」は必然。
同じ男性としてその様子を眺め、きっと多くを汲み取ってくれたであろうアキラさん・正さんが見せるとびきりの笑顔がとても優しくて印象的でした。
詩の繊細さに反して、サウンドが重厚でその音圧たるや山の如し。
ただただその轟音に心酔しつつも、私はその中で一際異彩を放っていたセンターの竜太朗さんをじっと見ていました。
まるで切り抜かれた異空間にいるかの様、傍観者の冷たい目線でじっとりと前を見つめ、詩を唇からダラダラと垂らしていく彼の姿を。
「ここで何が起きているのか」それを自分一人が理解できていないかの様に淡々と唄を紡ぐその姿と、思い思いに腕を挙げ全身を揺らす楽器隊・客席とのギャップ。
その絵に描いた様な「台風の目」っぷりが少々不気味で、「あぁ竜太朗さんはあくまでも竜太朗さんのままでいくのかな」と、そう予感させたのです。
ガッ!またも予想は大外れ。
そんな寝惚けた未来予想図に横蹴りを入れてくれたのが次曲『涙腺回路』でのことでした。
ウォーミングアップを終えた客席からはスモークと見紛う量の蒸気が。
イントロが鳴りだすとともに野獣の様な声をあげるオスオーディエンスの猛烈な高熱風が「Plastic Tree 有村竜太朗」の仮面を溶かしてしまったのか、A・Bメロから早くも「みんなの竜太朗像」がポロポロと剥離していく。
掠れ声で詩をグサグサと裂く様な歌唱に溺れている姿は、興奮を必死に抑えている様にも見えてコワイ。
そんなヴォーカリストの中身を引きずり出してやろうと言わんばかりの拳!声!押し!
その熱意に身を剥がされた竜太朗さんはここで豹変。
「腰折れちゃうんじゃないの?」と心配になるほど大きなアクションでギターを掻き鳴らし、ギターソロで突如お立ち台に飛び乗った彼は威嚇する様に狂乱フロアを見下ろす。
そして、彼は先程まで伏し目がちにしていたその瞳孔を引ん剥き!口をパッカリと開け!華奢な体を震わせながらマイクレスでこう叫んだんだ。
ウォォオオオオッ!!!
その一声に言わずもがな男たちは大爆発!プラスティックトゥリーぶっこわれ!
もう私は世界の終わりを感じたね。バンドこそ違えど、これは紛れもないドラゴンナイト(竜太朗狂乱ナイト)だ。
ここからはなんでもござれの煽り煽られ攻防戦。いや、攻攻戦。
守るべきものなどとっくに失った両者が殺り合うだけの話です。
竜太朗さんが両手で「もっと来い!」とジェスチャーをする度(この日だけで50回は確実にやっていた)に「上等だ」とばかり、ド級のシャウトをあげまくる野獣たち。
痺れを切らした竜太朗さんは身を大きく乗り出し、「もっと新しいもの見せてよ!」と声を荒げる。
その要求を迎え撃つ従順な男たちのドドド歓声にニコッと笑う彼の笑顔がなんとも綺麗でした。
これ以外にも何度か客に食らいつく様な目線で煽りをかましていた彼ですが、百倍の声が返る度にアーティストのタガが外れてしまい、思わず口角がプカプカ浮いてしまいます。
表現者たる表情さえ保持できない圧倒的な相思相愛が互いを讃え合って止まないのです。
きっと、あの場にいた全ての男たちがその笑顔を映す鏡の様な役割を果たしていたことでしょう。
竜太朗さんが照れた表情で「そんなに眩しい笑顔見せないでッ!」とおどけた姿は、想像力豊かな海月女子からすればさぞかし腰砕け。なはず。
最初のMCは、そんな竜太朗さんからでした。
「すごいね…きっと今日は歴史的な夜になると思っていたんだけど、想像以上です…結構長く生きてきたつもりだったけど、初めてのことってあるもんですね。楽しみで楽しみで昨晩眠れなかったんですけど、今日は暴れたくて仕方ない僕がいま~す。」
そう言って、出席確認時の生徒の様にペラッと挙手をする彼。
火に注ぐ油など向こうはいくらでも持っている様で、その手の発言がある度に客席からは精米機の1000倍を超える声量で対抗。声で会場が揺れるってこういうことか。
次から次へと投げ込まれる灯油ナンバーたちにフロアはボウボウ。
そんな中、私は「なんだこの曲!知らない!でも格好良い!また知らないの来た!けどやっぱカッケェ!」と一人胸中で大興奮。
そんな熱き楽曲の中に差し込まれた冷却材『Sink』。
ようやくリアルタイムで聴いていた曲がやってきました。
一秒前までの熱気を沈めるかの様に低体温で美しいイントロのギターが青いステージにこだまする。
語りかける様に切々と物憂げな声をもらす竜太朗さんを前に獣たちは静止。
最後列から見た客席の後姿、その頭上にテロップをつけるなら明朝体で「じーーーん」だ。
本来の姿に返ったかの様、実はバラードが大好きな男たちはその儚い世界の指揮者に導かれるまま、これ以上ない陶酔を見せます。
赤い月をずっとながめた
それだけでなんで泣くんだろう僕は消えたくなる
目に映るステージ、その景色を霞ませるギターは物寂しげな歌声を更に孤独にさせ、真っ赤なライトに照らされた竜太朗さんが『僕は消えたくなる』と顔を歪ませ声を大きく枯らせる。
「あの一瞬の景色を切り抜いて飾れるものなら」と切に願ってしまう程に息苦しく美しいシーンでした。
隣の男子が静かに泣いていて、私もちょっと危なかった。
同じ様な感情になったことのない詩の主人公の想いを聞いて、ここまでの感動を覚えさせるPlastic Treeは、失礼ながら改めて「プロだなぁ…」と打ちのめされるばかりです。
そのときばかりは欠片も声を上げず、アウトロの切れ間で惜しみない拍手を送る男たちへ竜太朗さんが宛てた「良い拍手だね。」の言葉と笑顔。これもまた言葉にならないほど素敵でした。
正さんが今日のライヴをするにあたって、こんな話をされていました。
「男だらけのライヴは工業高校に通っていた学生時代以来初です。初めてのことだから不安もあったんだけど、凄いねこれは。ねぇ君たち、今まで一体どこにいたの?」
『Sink』になぞらえ、「欠けた月の裏ー!」と返したいところでしたが、体の9割が羞恥心で出来ている私は迷わずだんまり。
そんなmeのことなど露知らず、客席からは「後ろの方にいたよー!」「俺もだよう!いっつも後ろだよう!」という泣きごとの様な返答が。
それに対してアキラさんが笑いながら「分かるよ!俺も山手線乗ってると同じ気持ちになる!痴漢に間違われるのが怖いんだろ!」と妙な煽りをかまし、「コワーイ!」と女子さながらの悲鳴をあげる弱者たち。
「一体なんなんだこれは…」と思いつつも、そういう様こそが「男」なんだよなぁとニヤニヤせずにはいられませんでした。
正さん「男限定ということで遠くから来てくれた人もいるの?ん?」
男A「大阪!」
正「お!大阪か!」
男B「福岡ァッ!」
正「おお福岡!凄いね!」
男C「三軒茶屋ー!」
正「めちゃ近いじゃん(笑)!」
なんてやりとりが笑いを誘ったり。
「男って凄いナァ。匂いとかがもうね…」と口にした竜太朗さんへ即座に差し出した「どんな匂い?」という客席からの問い。
少し顎をあげ、会場のにおいをクンクンと吟味した後の「うーん…焦げ臭い。」という寝ぼけ声での返答に変な歓声が湧いたり。
私は基本的にMC中のメンバーに茶々を入れる人があまり好きじゃなかったりしますが、この日の彼らは発言が冴えているのはもちろん、空気をきちんと読んで止めるところではガヤをピタッと止め、メンバーさんのメッセージを真摯に受け取る人たちばかりで、ひとつひとつのやりとりがとても心地良かったです。
メンバーさんもまるで古くからの友人と話す様な穏やか口調でした。
特にアキラさんは演奏中もずっとそうだった。
父親の格好良い仕事ぶりを客席の子供たちに見せている様、その誇らしげで頼もしい笑顔が大変印象的でした。得も言われぬ父オーラがね、すごかった。
でも、終盤は疲労感に打ちのめされた表情でしたけどね。お疲れ様です本当に。
拳・ダイブ・モッシュ・ヘドバン・折りたたみ・その他フリーダム(コサックダンスしてる人もいた)なんでもござれな無法地帯と化した客席で眼鏡を落としてしまった人がいて、結果的にフレームが折れてしまったんだけど、それを察知した竜太朗さんが「え?眼鏡折れた?」と問い掛け、当事者の男性が破損眼鏡を掲げ見せてみたところ、「あーアロンアルファで直るよ。」と軽くあしらう。
「あらやけに冷たいわ」と思ったそのとき、なにを思ったか「みんな!眼鏡君に!盛大な拍手を!」と大声をあげた竜太朗さんのサイコパステンションに戸惑い混じり、訳のわからない大歓声が湧いたり。
もうきっかけさえあればいつでも炎上してやる勢の男たちにとって、あの二時間におけるウォォオオオ率たるや病的なものでした。
私的には、その話題が一段落したときにアキラさんがボソッと言った「いや、アロンアルファじゃ直らねぇだろ。」の呟きがなにより面白かったんですけどね。
あと、これはアンコール明けのこと。
ステージに男山酒造の酒樽(男限定とかけたのかな)が用意されていて、「石原軍団がやるあれだ!」とウキウキした口調の竜太朗さんが。
どうやら今日参加しているお客さんからの差し入れだったらしく、一人の男性が「俺からです!」と挙手をしたところでまたまた歓声が湧き、竜太朗さんが「あなたさまのお名前は?」と丁寧に尋ねたところ、「カタオカです!」と彼。
すると、もうここからは男子高生のノリ。鳴り止まないカタオカコール!
一度のみならず、二度も三度も湧いたそのコールが鳴り響く度にゲラゲラと笑うアキラさんの笑顔が忘れられません。
そんなアキラさんは「普段こんなんじゃないから。こんなに汗ダラダラかかないよ。クールな男なんでね。」と言い、それに対してヒューッ!と茶化す面々。
その隙間を縫って「熱い男アキラァァァア!」と叫んだ男子をビシッと指差し、「おう!もう今日はそれでいくわ!」と返せばまたしても怒号。
マンネリ知らずの声はもはや天災の域に達していました。
そして、記憶から切っても切れないのがアンコール待ちの時間のことでした。
メンバーさんがはけた直後、「プラスティック男子サイコーッ!」と一人が雄叫びを挙げようものなら、一斉に加担してウォォオオオ!と賛同する群衆。
その流れで、アンコールの掛け声はまず「プーラ男ッ!プーラー男ッ!」から始まりました。
しかし、それにすぐに飽きたのか、今度はメンバーコールが発生。
予め決められたタイミングなんてないのにも関わらず、徐々にメンバーの名前がグラデーションで変化していく見事さ。
これは結構長いこと続いたのですが、激烈なステージングをこなしたメンバーさんは酷くお疲れなのかなかなか出てきません。
すると、ここからは男の独壇場。
駄々以外の何物でもない罵声がステージに投げつけられます。
「じらさないでーーーッッッ!!」
「女いないんだから髪直したってしょうがねぇだろー!!」
「こっちは準備万端だ!早くしてーーッッ!!」などなど。
ひとつのヤジが飛ぶたびに笑いが起きて、女子からすれば「なんて低俗な!男って!」な一幕も、あの空間では優秀なる起爆剤となって機能してくれていました。
一通り止んだところで、一人の男性が拳を振り上げ「ボーイズドンクライッ!ボーイズドンクライッ!」とこの日の公演タイトル叫び始め、「おぉそれいいね!」といった反応を見せた一同がまたも加戦。
しかし、アンコールの掛け声というのはどういうわけかどんどんペースが速くなってしまうもの。
「ボーイズドンクラッ!ボーイズドックラッ!ボーイズドッ!」と完全に舌が回らなくなった一同に発案者が「これ無理だッ!」と大声で詫びを入れ、これまた場内大爆笑。
そうまでしても出てこないメンバーさんに「もうネタ切れだようッ!」と声に出してゴネ始める面々。
途中途中でスタッフさんがステージに現れてはメンバーと勘違いして歓声を浴びせる彼らの無邪気さ。動くものには何にでも突っ込むサイの如し。申し訳なさそうにササッと忍び足で去っていくスタッフさん。本当にお疲れ様でした。
なかなか出現しないプラスティックな面々に新たな案が。それはなんとも単純明快な要求。
その名も「ハ・ヤ・クッ!」コールでした。
心情とピッタリ合ったこの合言葉を武器に抜群の一体感を見せる我ら。
その後、ほどなくしてステージが白いライトに照らされ、またしても第二次渋谷対戦の幕開けです。
「こんなに鼻水出るライヴ初めてだ。僕ら一応ヴィジュアル系なんで髪直そうと思ったんだけど、鏡が蒸気で曇り過ぎて何も出来なかった(笑)。湿度86%だって。」という竜太朗さんからの惨状報告になんだか誇らしげな男たち。
アキラさんは「体感温度でいうと、人の体温と変わんないよ今。男って本当にすげぇな。思い出したよ。ライヴハウスって暑いところだったね。」と。
その一言に余計調子づいたフロアはウオウオ悶えながら、次の攻撃に備えます。
竜太朗「アンコール。呼んだな?呼んだっていうことはまだまだいけるんだな?もうこうなったら俺らと君らの体力勝負だ。まだまだやらせてよ!もっと遊ばせて!もっとだよもっとッ!(狂)」
その言葉からお互いどこまで体力あるんだと疑い合いたくなる様なコールアンドレスポンスの熱気。
どの楽曲も凄まじかったですが、『メランコリック』『サイコガーデン』はその絶頂を極めていました。
「このタイミングでメランコリック来たらマズイ!」と思いながらも、心のどこかでそれを期待をしていて、実際そのイントロが流れ出した瞬間なんてどこかへ逃げ込みたくなる程の惨事でした。
爆発の瞬間に場内を襲った正さんの野太い掛け声に「大歓声」という名の怒号リンチで返すフロア。
「これがやりたかったんだ!」って感情が溢れ出し過ぎ!分かりやす過ぎるぞ男子!
あの声量ばかりはどう足掻いても言葉じゃ表現できないから、必殺の精米所で例える。2300倍だ!
一曲一曲のイントロ・ギターソロに湧きまくる歓声を愛おしそうに受け止めながら、後半の楽曲では隙さえあれば客席にマイクを預ける竜太朗さん。
いつどんなタイミングでマイクを向けられても、迷うことなく大声で合唱する男性陣を見ては、「あぁ間違いなくこの人たちはPlastic Treeが好きなんだ」と、至って当たり前なはずの事実に感動させられました。
三次元にいるとは思えない雰囲気とオーラをもつ竜太朗さんなのに、結局2曲目から最後まではずっと理性放棄の発狂ちゃんでした。
歓声依存症というか、完全なる中毒になっていた。怖いくらいだった。
客席を喰っちゃうんじゃないかと思うほどに何度も大きく口を開いて、生声で目の前の獣を煽り散らすという、完全なるミイラ取りがミイラになっちゃった典型例。
正さんが「今日のライヴ、本当にやって良かった。女子海月が見たらホンッッットに悔しがると思うよ。男に生まれて良かったですねー。」としみじみこぼし、男限定ライヴを今後もやるかどうか今日の様子を見て判断すると決めていたそうなのですが、考えるまでもなく恒例化していこうという話をされていました。
男D「毎月やって!」
正「毎月は無理かなー。でもなんかキュンキュンしちゃうよね!」
男E「抱いてー!」
正「抱くのは無理かなー。」
そんなやりとりが交わされた後、竜太朗さんが「これで最後なわけねぇだろ!ずっとやっていこうよ!絶対またやろう!」とここ一番に声を張り上げたときの歓声がこの日のピークだった様に思えます。
竜太朗さんはその後も「忘れられないよ今日は。」「絶対またやろう!また遊ぼう!絶対だよ!」と何度も繰り返していました。あの場にいる誰よりも強く願っているかの様に。
「絶対的に楽しい今」という時間に溺れながら、終わりの時間が近付いていることへの寂しさを隠しきれない表情。
この二つの言葉を張り上げる姿は、まるで約束がなければ生きていけない寂しがりの子供の様でした。
『サイコガーデン』でもはや完全に人間の上限を越えるパワーを放出した254人。庭の形をした地獄へようこそ。
正さんは「サイコガーデンで締める予定だったんだけど、そうはいかないでしょ!もっと声出るだろ!もっと!」と煽り、竜太朗さんがトドメの一言を。
「なんで(もう一曲)やるかっていうとーーーお前らを暴れさせる為だろうがぁぁああッ!!」
くるっとこちらへ背を向け、手を高く掲げた後『Ghost』のタイトルコールをすると…
その後の惨状模様は御想像にお任せしましょう。
ただひとつだけ、どんなに想像のハードルを上げられようとも軽く飛び越えてしまう程の絶景だったことをお伝えしておきます。
終わりを恐れるかの様にアウトロを長く長く長く。
そして、一瞬の隙間もなくドロドロの客席を煽り倒す竜太朗さん。
照明に照らされた汗光るいくつもの腕と拳が空を埋め尽くす。
満面の笑みを浮かべながら、最後に解き放った全身全霊の「男子限定!こんなに楽しいと思わなかった!お前ら最高ダァァアア!」の声。
完全なる250のスピーカーと化した客席の一人一人からも満場一致の大歓声が湧きました。耳割れそうだった。
男性限定ライヴは過去に4バンドほど拝見したことがありますが、ノリの激しさから言い合いや喧嘩みたいなものが始まることもしばしば。
でも、この日の場内は隅から隅まで同じ笑顔に溢れていて、それこそ言ってしまえば「ぶつかってごめんなさい」なんて細かな謝罪もなし。
暗黙の了解として「今日は細かいこと言いっこなしで、お互い目一杯楽しもう」という雰囲気と意識の一体感が素晴らしかったです。
相思相愛を絵に描いた様な、実に馬鹿らしくて、最高に子供じみていて、すべての人が幼児化した我儘勝手愛溢れる一夜。
あの時間に居られたことをとても嬉しく思います。
「メンバーを楽しませよう喜んでもらおう。僕らも楽しもう共に喜ぼう」
極めて純粋なその願いがあんなにも蔓延した公演を私は知りません。
もみくちゃのフロアで人が崩れようものなら一斉に詰め寄り、助け合う。
助ける側も助けられる側も曇りひとつない笑顔を見せる。
竜太朗さんが身を乗り出してその手を客席に伸ばそうとも無理に掴むことも引っ張ることもなく、行儀良く真っ直ぐに腕をのばし演者の高揚を煽る。
酸欠状態なのか、はたまた水分が出切った状態で飲んだ日本酒にやられたのか、フラフラとステージ際を歩く彼が客席へなだれこみそうになったときは、きちんと支えてステージへ返してあげる。
それまで「ダイブ」という行為に不安の声をもらしていた竜太朗さんが最後に客席へ飛び込んでみせたのも、ステージへ戻った際の合掌越しの笑顔も、何度も何度も繰り返される感謝の言葉もすべて、この一夜で築いた男同士の信頼が勝ち得た功績なのだと思います。
「ありがとう。」
終演を迎えても尚、鳴り止むことを知らないその言葉と拍手に胸が熱くなる。
いつもはライヴが終わったらすぐに会場を出る私ですが、昨日ばかりはそこから離れたくなくて彼らと同じだけの拍手を送りました。
まぁ言うまでもなく、地上へ帰る階段ではみんながみんなヘットヘトでおじいさんみたいでしたけどね。
「その場限りのこと」
その為に一生懸命になれる人は、アーティストであれファンであれ最高に格好良い。
それを改めて思い知らされた価値のある一夜でした。
こういったライヴでは女性がないがしろにされる様なMCや男性の主張が勢い任せにうっかり出てしまうのが常ですが、Plastic Treeのメンバーさんからはもちろん、あれだけ自由に喋り続けた場内の男たちからもそういった言葉が一つもあがらなかったのが素敵でした。
女性への対抗心めいた台詞といったら、たった一度だけ客席から湧いた「女子に負けないぞーッ!」くらいなものです。
でも、これは全く好戦的ではないし、むしろ可愛い。そして激弱!
はてさて、思い出に浸るのもこれまで。
正さんが「言い忘れない様に」といった様子で客席に投げかけてくれた「いつもの、普通のライヴにも来てね。」というお言葉に甘え、今後は私が彼らから目を離していた時間に生きていたPlastic Treeの「今まで」と「これから」を迎えに行くとします。サイコガーデンッ!