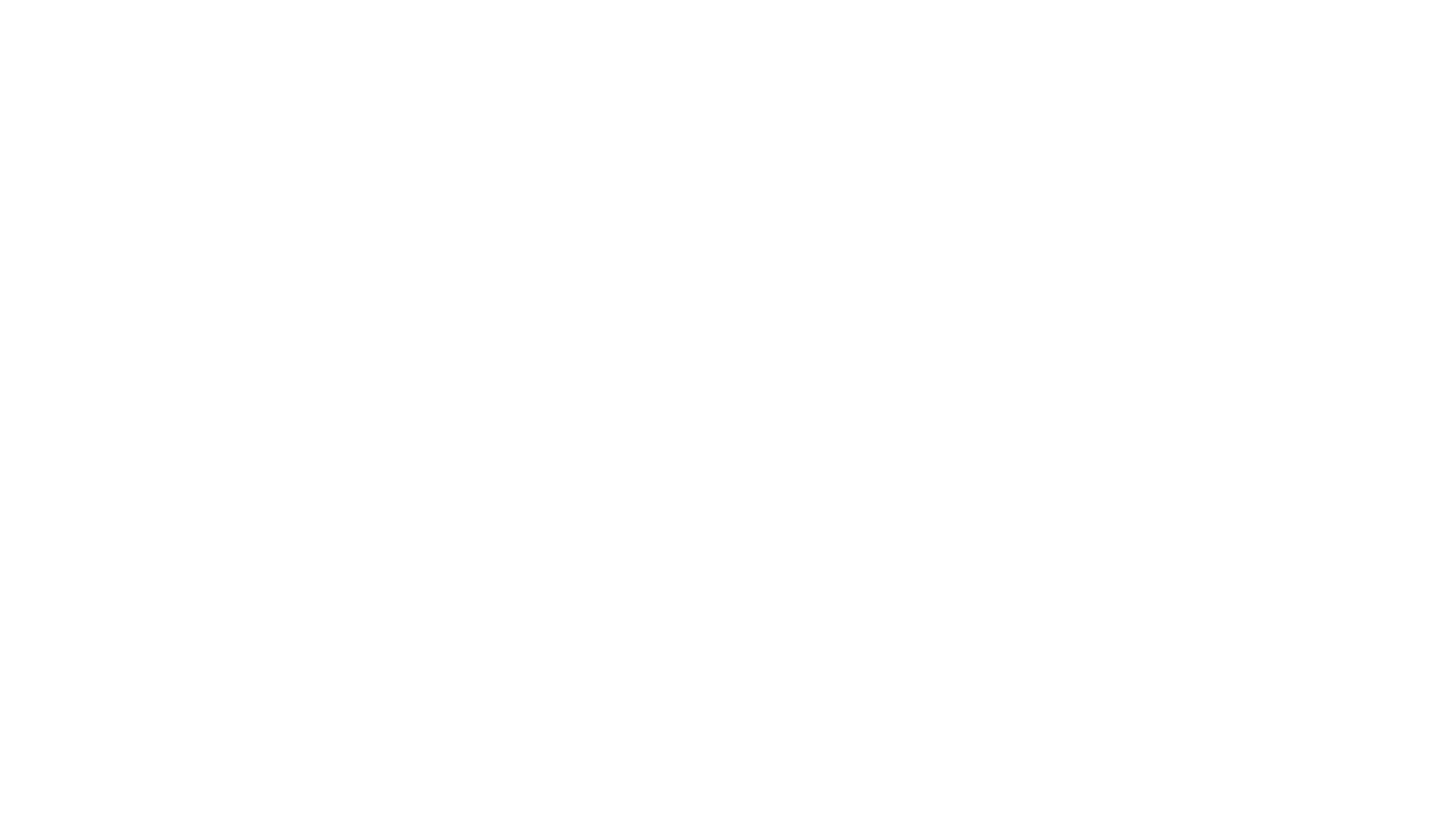その衝撃は、当時中学一年生だった無垢な私に容赦なく襲い掛かった。
日常的に目にしていた「バーチャル」がある日「リアル」へ変化してみせたのだ。
そのときに生まれた恐怖にも程近い感動は、いつまでも色褪せないまま私の胸のなかに生き続けている。
今から御覧いただくのは、あの日までの私にとって「実体」ではなかった存在が、三次元の世界で目の前に現れたときまでの出来事を綴ったマジしょうもないノンフィクションストーリー。お代も苦情も結構結構。では、はじめます。
「劇的な出会い」とか、「運命」とか。そういったものとは全く違う。いやむしろ、私が彼らの世界に触れるのはあまりにも現実的で、その上どうしようもないくらいに「日常的」なことでした。
私を「年齢=ヴィジュアル系ファン歴」な怪物に仕立て上げたのは、紛れもなく10歳離れた長男の仕業…
私がまだ幼稚園にすら入っていなかった頃から、この身を愛ある洗脳へと陥れてみせた彼は、ロックバンド「BUCK-TICK」の熱狂的なファンでした(超現在進行形)。
当時住んでいた「一軒家」とは名ばかりの古びた木造住宅。
彼が大音量で流すけたたましい爆音の正体が「BUCK-TICK」というツンツン頭集団によってもたらされているものだと知ったのは、それからずっと先のことでした。
そりゃあもう毎日聴いていた。
いや、「聴かされていた」の方が圧倒的に正しい。
なんだってんだホントに。うるさいったらありゃしない。
朝食を食べるとき。
食パンを焼くオーブントースターのチンッが全然聞こえない。うるさい!
母と買い物に出掛け、家へたどり着くまでの道の途中からでも聴こえてくる『TABOO』。うるさい!
近所からの呆れ混じりな苦情すらも掻き消すその轟音と、それに合わせて熱唱する兄の声。うるっっっさい!けど、まぁまぁ上手い!!
そんな日々が一年の内およそ365日続く環境に身を置きながらノイローゼにならなかった時点で、私は幼くしてBUCK-TICKファンになる素質があったのでしょう。
とはいえ、園児だった私には髪も神経も尖りきったロックバンドの曲の意味など分かるわけがありません。
ただそれでも毎日毎日大音量で同じCDを聴かされ続けていれば、嫌でも覚えてしまうのが無駄に多感な園児脳。
くわえて、そんな私に「わかんない」と言われ続けても尚、飽きずに毎日BUCK-TICKの知識を植えつけてくる彼。
こやつもまた、15歳にして相当な幼児脳の持ち主だったことを今になって知るのです。
「もりのくまさん」よりも「悪の華」を先にマスターしてしまった私の人生は、生後5年にしてヴィジュアル街道まっしぐらなレールを走ることとなるのでした。おおこわやこわや…
我が家は特別貧乏ではありませんでしたが、電化製品の導入がえらく遅い家庭でした。
そんな埼玉の小市民ハウスにCDラジカセがやってきた日のことは、あれから30年が経つ今でもまるで昨日のことの様に思い出します。
あの日がなければ私はBUCK-TICKを知らぬまま、今日を健やかに健全に生きていたことでしょう。ラジカセで人生変わるのは何もコタニキンヤだけではないのです。
CD1枚とカセットテープが2つ入る真っ黒なステレオラジカセ。
それがやってきてからというもの、毎朝、毎昼、毎晩。ガンガンと古びた木造住宅を刺激し続けたBUCK-TICKサウンド。
当時、彼らがCM出演していたラジカセのキャッチコピーでもあった「重低音がバクチクする」という言葉。
それを知るよりもずっと前に、私はその現象を目の当たりにしていたのです。あろうことか、本来どこよりも居心地がいいはずの自宅でね。
「バクチク」というより、あれはもはや「バクゲキ」だった。
毎日LからRからとめどなく撃ち落される爆弾。よく生きて三十路を迎えられたものだと感心します。
そして、いくらか時が流れ、当時の私にとって「音」と「写真」でしかなかったBUCK-TICKが「映像」でやってくる時代へ。
そう、我が家に「ビデオデッキ」なるものがやってきたのです。
「Victor」と大きく書かれた外装箱を開けた瞬間、革命的な御姿をされたビデオデッキ様との対面に父以外の4人が思わず声を上げたものです。
まだケーブル類を差し込んでもいないというのに、兄の手には一本のビデオテープが構えられていました。
彼がお小遣いを一生懸命貯めて大奮発中の大奮発で手に入れたそれは、ビデオデッキがやってくる前から家にあり、しかし、再生機器がないためにずっと観られずにいたものでした。
テープの箱には、アルファベットの概念なんて皆無の5歳児にさえ理解された悪魔の文字列「BUCK-TICK」。
機械に強い次男が難なくケーブルを繋ぎ、それを跳ねのけるようにして挿入されたライヴビデオ。長男にとって、待ちに待ちに待ちに待った時間の到来です。
「ここに座れ」と指示され、兄が慣れない手つきで再生ボタンを押したその夜、私は初めて「動くBUCK-TICK」との対面を果たします。
「格好良い」だとか「綺麗」だとか分かるはずがない。
「変な人たちだ。太鼓の人、幼稚園にいるニワトリみたいな頭してるなぁ」くらいの感想。
ただ、「音楽が好き」という感覚が芽生え始めた当時の私にとって、「あの歌たちは、この人たちがこうやって作ってるものだったんだ」という視覚的な衝撃は計り知れないものでした。
ドラムはおろか、ギターとベースなんて目にしたこともなかったですからね。
言うまでもなく!それはもう言うまでもなく!その日からは毎日毎日動くBUCK-TICKを観せられる日々が続きます。
家に貼ってあったポスターとは違い、金色の長い髪をおろした櫻井(と、当時は兄と呼び捨てで呼んでいた)がキンキラに光ったマネキンの上半身だけを抱えて妖艶に歌う姿。
兄はその瞬間が近付く度にいちいち画面を指差し、「ここがかっけぇんだよ!」と熱心に語ります。やっぱりうるさい。
興奮するたびに一時停止を押す彼の手癖により、本来であれば一時間やそこらのライヴビデオを見終えるのに3時間は要するという怪奇現象がつづくのです(人はそれを「BUCK-TICK現象」と呼ぶんだとか)。
嬉々としてそんなストップ&ゴー劇を繰り返す兄でしたが、生憎当時のビデオデッキは一時停止をすると画質が著しく荒れる仕様でした。
よって、その「かっけぇ瞬間」を上手く私に伝えられない悔しさから、彼は同じ失敗を繰り返すたびに「アァ゛ッ!!」と威勢よく嘆いていたものです。うるさい。
しかし、当時は今よりまだ素直だった私。
「え!どこがかっこいいの!?」と、画面を食い入るように見つめる弟の姿に彼はとても満足そうな笑みを浮かべ、ああだこうだと見所を説明してくれました。
そんな日々もまた、何年と続きます。
懲りずに兄は、同じビデオの同じ場面で「ここがかっけぇんだよ!!」と連日シャウトに大忙し。
そんな日常風景のなかで、兄が注目している「かっけぇ場面」とは違う、自分なりの「かっけぇBUCK-TICK」の瞬間を見付けるようになっていた私がいました。
でも、兄には決して「ここ格好良いよ!」とは教えず、秘かに「僕だけのかっけぇBUCK-TICK」をキャッチしては秘かにニヤニヤしていたのです。
新しいCDが出るたび、兄はそのジャケットを自慢げに見せてきます。当然、まだ8cmCDです。
その細いジャケットは小さい私の手にも持ちやすく、兄が学校へ行っている間、じーっと読めもしない歌詞カードを目で追っていました。
母親が聴かせようとしている「みんなのうた」のカセットテープなど「そんなのかっこわるくて聴いてられるか!」と断固拒否していた当時の私に言いたい。
「そっちを選ぶ人生も多分結構良かったぞ…」と。
そして、そんなドメスティックな生活を続けながら、園児は小学生へ。
もうこの頃には完全なる「BUCK-TICKファン」と化していた私は、小学生になってからも毎日毎日兄と一緒になって画面&スピーカーにかじりつきます。
その一方で、うるさい音楽全般を嫌う次男はそんな私たちに呆れた顔をしながら、L⇔Rやらユニコーンやらマッキーやらを静かに嗜んでいました。
長男と私。
このバカ二人の間には、ひとつの暗黙ルールがありました。
それは、「兄のいない時間は決してBUCK-TICKのビデオを観てはいけない」というもの。
今思えば、至極くだらない決まりですが、私は何故かそれを守っていました。
なんだかんだ言って、兄と一緒に話をしながら観るBUCK-TICKが好きだったのでしょう。
もしくは、「鶴の恩返し」を幼稚園時代に読んでもらったことが原因だったのかもしれません。
「ビデオを再生したらヤガミが自毛でウィッグを作っていた」なんて、トラウマ以外の何物でもないですしね。
言いつけを守る健気な三男こと私は、兄が帰ってくる時間の少し前になるとテレビを付け、棚にあるビデオテープのケースをドキドキしながら見つめていました。
こんなくだらない決まりを作ってまで、10歳離れた私と対等に音楽を楽しもうとする兄がとても「子供っぽい人だった」と気付くのも、やはりずっとずっと先の話でした。
ターボレンジャーやドラゴンボールを夢中で見ている友達と駆け回りながら、私の目にはBUCK-TICK・BOOWY(斜線入らず)・LUNA SEA・D’ERLANGERしか映りません。
なんちゃら戦隊よりも遥かに強そうで、どんな悪者キャラよりもずっと不気味な彼らに心を惹かれて仕方なかったのです。
外では砂遊び、中ではBUCK-TICK。
そんな日々が小学校高学年まで延々と続いたある日、私の耳に大きなニュースが飛び込んできます。
それは、大の仲良しであった兄が家を出ていくことになったという報せ。
彼は、当時付き合っていた彼女と結婚することになったのです。