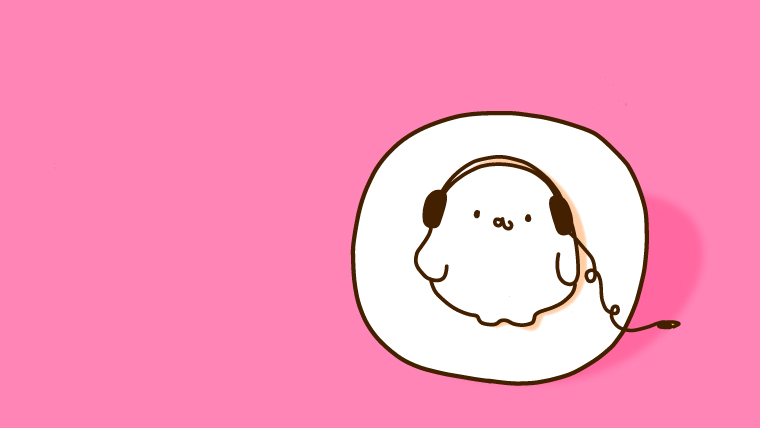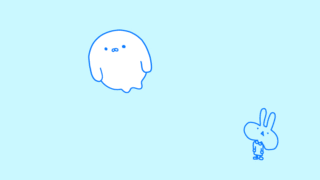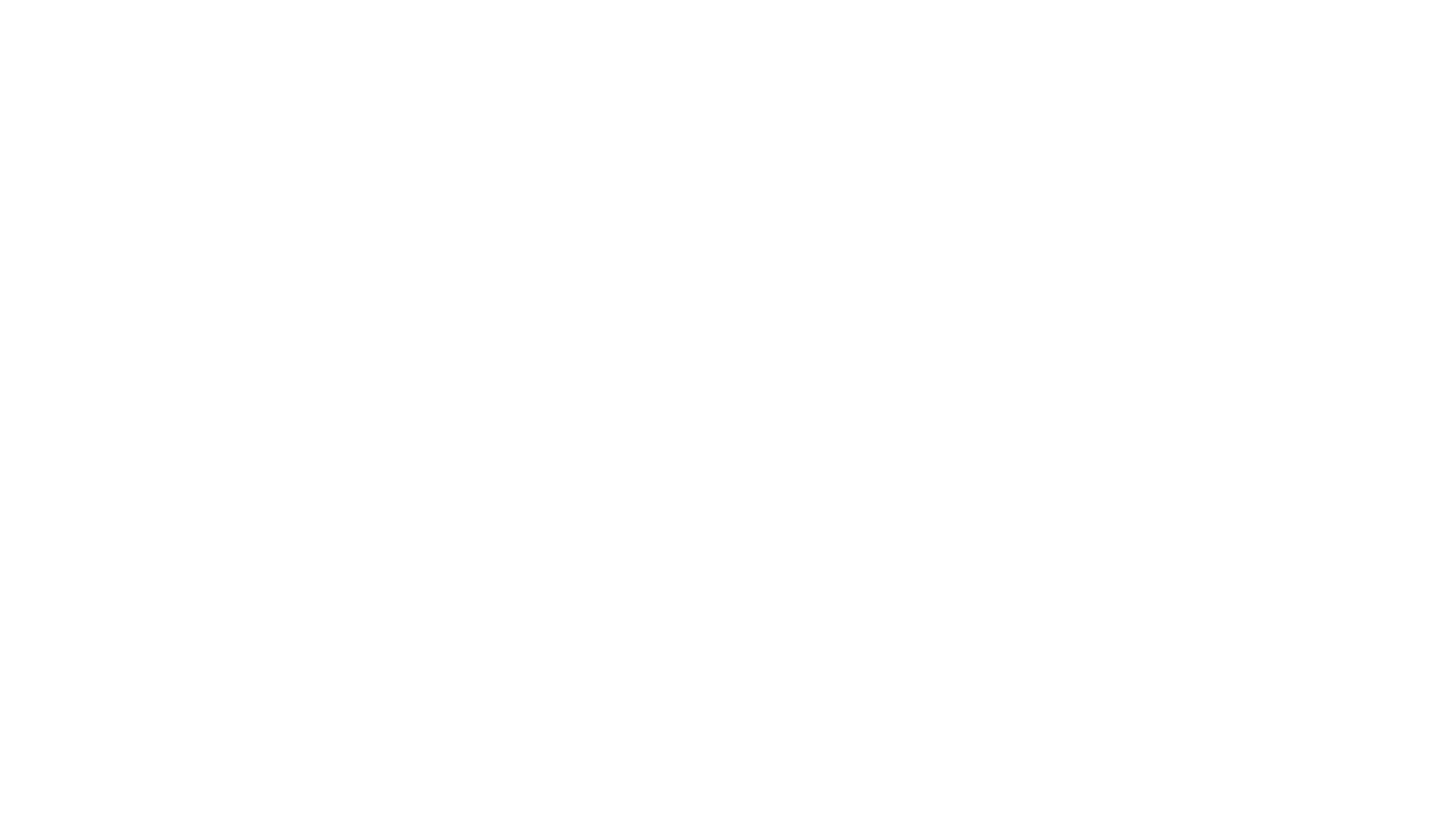小学3年の頃、学校の近くに30階を超える高層マンションが建った。
この辺りのマンションというとせいぜい5階建てがいいところだったので、地元民にとってその居様はSFそのものだった。
改めて言わせてほしい。このマンション。とにかく高い。
建設中はずっと黒い網が掛かっていたので全容が掴めず、教室の窓からその黒の巨人を眺めては「何ができるんだろ…」とクラス中で噂する日々が続いた。
いざベールを剥いだときには全生徒が大興奮で「はじめてのこうそうまんしょん」を指さしはしゃいだものだ。
当時からあまりみんなとワァワァするタイプではない私だったが、その堂々たるそびえっぷりにはさすがに高揚してしまい、掃除の時間にベランダへ出て黒板消しをパンパンと叩くときには決まって、「あれがこっちに倒れてきたらここまで届くのかなぁ」なんてことを考えていた。
みんながマンションに釘付けな中、霊感の持ち主であることをやたらとアピールしたがる橋本(女子)が「夜になるとあのマンションの屋上に髪の長い女の人が立っている」とおどろおどろしげに話した。
虚しいものでその話を信じる者は誰一人としておらず、それに腹を立てた彼女は「明日とかに絶対祟りが起きるからね!私言ったからね!」と顔を真っ赤にして叫んだ。
翌日、彼女の予言は的中することになる。
なんと、橋本が学校で大切に飼っていたメダカを上級生が誤って流し台に流してしまったのだ。
必死に謝罪する上級生の声になど一切耳を貸さず、「これは屋上の女の祟りだ!みんなが信じないから!」と号泣する彼女の姿を見て、メダカにこれっぽっちの興味もなかった我々はどんな表情をしていいものか分からずにいた。
SFマンションにもある程度目が慣れてきたある日、帰りの会で担任の先生が「明日からこのクラスに新しく3人のお友達が来ます!」と言った。
「転校生」という響きは小学生だった我々にとって給食の「アイスクレープ」と同等のキラメキをくれるもの。それも一気に3人ときたもんだ。教室が沸かないわけなどなかった。
お調子者の大熊が「そのひとたちはドラゴンボール好き!?」と前のめりで先生に尋ねたが、「先生は知りません」の冷たい一言であっさり一蹴されたときのあのなんとも言えない空気感が未だ脳にこびりついて離れずにいる。これも屋上女の祟りだろうか。
翌朝、案の定教室は転校生の話題で持ちきりだった。
どうやらうちのクラスだけではなく、他にも4人の転校生が来るとのことで、会話の熱は上昇するばかりだ。
チャイムが鳴り、先生と共に転校生ズがやってくると、先程までのざわめきとは一変、生徒は静まり返って彼らを凝視した。
先生の左には、肌が浅黒く見るからに運動神経の良さそうな米望(よねもち)と細谷(ほそや)、そして2人とは対照的に色白で全くこちらを見ようとはしないシャイな村井。
転校生は全員男子だった。
前日にあれだけはしゃいでいた大熊は、3人の自己紹介が終わるのを合図にガタッと席を立ち、算数の授業で使っていた計算用のタイルを口にくわえながら「デリシャ~ス!」と叫ぶお得意のジョークを披露したが、3人から「無」のリアクションを食らい、100点満点の苦笑いを浮かべたまま静かに着席した。
3人は一ヶ月もしない内にクラスに溶け込み、つつがなく夏休みへと潜り込んだ。
このとき、我々と同列であるかの様に思えた彼らが脳ある鷹ちゃん集団であったことなど知る由もなかった。
その事実をまざまざと思い知らされた日のことを話そうと思う。
それは、夏休み明けの登校日。
宿題の提出を終えた我々に、先生が「みんなは夏休み中どこへ行きましたか?」と聞いてきた。
あちこちから「おばあちゃんち!」「としまえん!」「大和田プール!」といった声があがる。
聞かれてもいないその場所でのエピソードを思い思いに語るクラスメイトだったが、直後に宙を貫いたまるで聞き覚えのない横文字に言葉を失うことになる。
「マレーシア!」
教室は静まりかえり、一斉に声の出元を探った。
米望だった。
「マレーシアにも家があるからそこに行きました」
しばらく静まり返った後、我々は近くの席の生徒とコソコソ話を始める。
「家がふたつもあるの?」
「マレーシアってどこ?」
「浦和の方だよ」
コソも積もればザワとなり、そこには米望の声量を遥かに上回る「マレーシア」の五文字が充満していた。
今の時代はどうだか知らないが、1985年にリリースされた小3児の頭に「海外」なんて概念は存在しなかった。
そして、マレーシアのザワめきがある程度落ち着いた教室に、この日2つ目のミサイルが投下される。
「オレはオーストラリアに行きました!」
おーすと…なに??
転校生2号の細谷が放ったその一言に再び混乱する面々。
しかし、子供というのはなかなかに賢く、それが海外ということまでは理解していなくとも「なんとなくマレーシアと同じような感じなんだろうな」とだけは察していた。
当時から頭が悪かった私も「埼京線で行けるところではない」という確信を抱いていたので、少年期の類推能力は馬鹿に出来ない。
2人の発言が教室を支配した後、我々の視線は必然かの如く一点に向けられた。
そう、3号のシャイな白肌君こと村井である。
「で、お前はどこ行ったんだ?」という熱視線に震え、彼はその真っ白な顔に少量の青を混ぜながらこう呟いた。
「Windowsで遊んでました…」
う、ウインドウズ…それってマレーシアより遠いの…??
分からないものに対していちいちリアクションをすることに疲れた我々は、近隣の庶民勢と耳打ちをする気力さえ失っていた。
「帰ったら母に聞いてみよう」と思った私は、連絡帳の最後のページに「マレーシアウインドウズ」と書いた。「オーストラリア」は覚えられなかった。
現にこれを書いている今も細谷がバカンスを楽しんだ場所がオーストラリアであったかどうか曖昧だったりする。
明らかに既存の生徒とは異なるオーラを纏った3人には、ある共通点があった。
彼らは皆、例の高層マンションに住んでいたのだ。
当時は「富裕層」なんて言葉も定義も知らなかった我々だったが、その事実を知ったときに「あのマンションに住んでる人はすごい」という共通認識を得ることになる。
そんな3人のなかでも細谷は特に存在感が突出しており、オーストラリア発言以外にも多くのカルチャーショックを我々に与えてみせた。
その特筆すべきものが「言葉」だ。
彼が初めて学校に輸入してきた多くの言葉のなかで最も校内に普及した「チャリキー」という単語。
自転車の鍵のことをいうのだが、当然我々はそんなハイカラワードを聞いたことがなかったため、初めて彼の口からその言葉を聞いた際、「ん?チャリキ?なにそれ?」と庶民同士で泳ぎ切った目を見合わせた。
しかし、なんとなく「それってどういう意味?」と聞くのは恥ずかしかったため、その意味を知るまでに一ヶ月以上の時間を要することとなった。
誰よりも先にその言葉の翻訳に成功した吉尾(蛙飼いのアウトロー坊や)には尊敬の眼差しが向けられたものだ。
細谷はこの他にも「腰パン」「パクり」といったニューワードを次から次へと埼玉へ仕入れ、転入から一年足らずで校内随一のトレンドリーダーに。
彼の周りには、そのセンスに憧れた男子生徒たちがワラワラと群れを成していた。
アディダスのジャージをお洒落に着こなし、ミサンガを巻いた鍛え抜かれた足で50mを誰よりも早く駆け抜ける。
そんな彼が女子からモテにモテモッテだったことなど言うまでもない。
彼に限らず、転校生はいつだって新しい風を連れてきた。
特に印象的だったのは、中2のときに越してきた長身女子佐藤だ。
彼女は中学生らしからぬ色気を振り撒き、容姿だけでなくその内側までもマセきっていた。
なんとなく近寄りがたい印象もあり、男子人気こそそこまでなかったが、クラス中の女子が彼女に憧憬の眼差しを向けていた。
転入初日、彼女は給食で出たさくらんぼを片手に「この部分(へた)を口の中で結べる人はキスが上手いって知ってる?」と言った。
班員であり、オトナシイオブザイヤー最多受賞中だった尾田はその唐突なアダルトクエスチョンに硬直し、見る見るうちに頬をさくらんぼ色に染めていく。
佐藤に魅せられた彼女は、その無添加無着色な心のスポンジにパープルな入れ知恵をぐんぐんと吸い込み、半年後には「同学年の男は子供すぎて無理」とまで口にする様になった。
その後、尾田は国語教師と関係を持ったことが問題になり、教師共々学校から姿を消した。
無垢であることの難しさを知ったのはこのときだった。
私は転校の経験がなく、いつもワクワクしながら待つ側の人間だったが、もしかしたら今この文字を退屈そうな眼差しで追ってくれている方のなかに転校経験者がいるかもしれないので、液晶越しにちょっと尋ねてみたい。
親から転校を知らされた日のこと。
それをクラスメイトの前で話したときのこと。
転入前日の夜のこと。
初めて担任と会話をしたときのこと。
みんなの前で自己紹介をしたときのこと。
そのときどきに生まれた感情のひとつひとつを。
「うちはパパが転勤族だったから慣れたもんよ」という方は「達観の主」と認定し、「一度限りの転校」を経験した方の感想をどこかで聞けたら嬉しいなぁと思う次第。
教えてくださる方がいたら、スクロールするその指に念を込めてお伝えくださいまし。
文字にせずとも伝わるのよ。iPhoneならね。
というわけで、今日は「転校生は文化密輸の常習犯」というお話にお付き合いいただきました。
寒くて暑くてやんなっちゃうハロウィン手前ですが、好きな音楽でも聴きながら引き続き良い夜をお過ごしください。