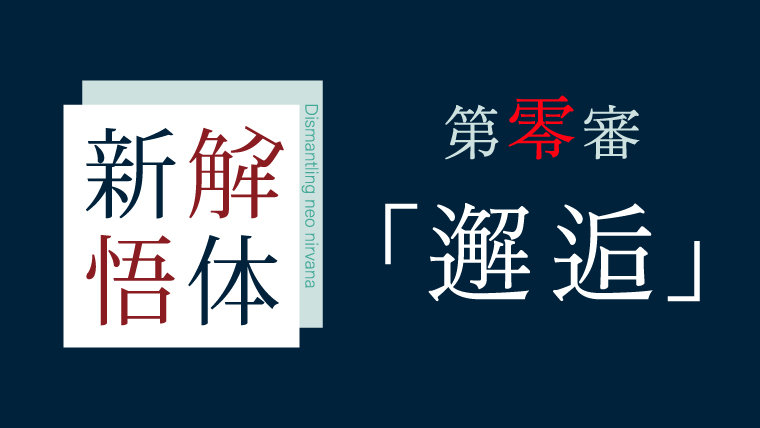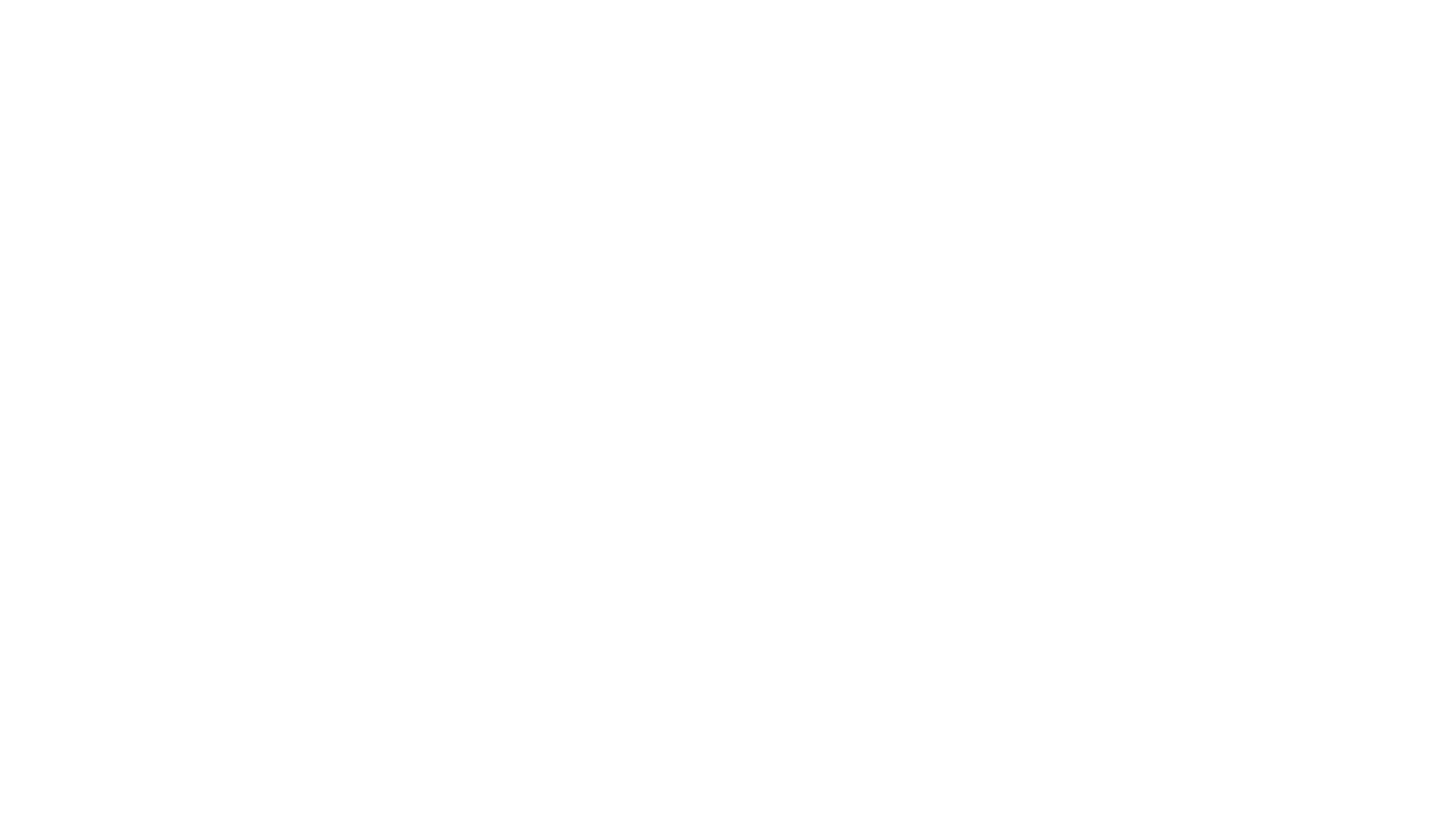雑談の最中、唐突に録音開始──
久我:(アイスティーの氷をカランカラン鳴らしながら)いやぁ~渡邉さんもお酒飲めればなぁ~。
──そうなんですよ。酒屋で長く働いていたくせに一滴も飲めないんですよね。
久我:(録音前までの話題が)お酒入れながらしたい感じの話だからなぁ。やぁ面白いですよ。
──「何言ってんだか分からない」って周りから散々笑われてきたので、そう言っていただけると嬉しいですね。でも、もうつまらないことは見るのもやるのも嫌なんですよ。
久我:それはそうですねぇ。うちもバンドがコロナでしばらく活動できなくて、戻ってからも情勢は変わらず、それ以前には渉君の脱退や事務所の問題もあって、実際にお客さんもすごい減っちゃってるんですよ。コロナが明けたとしても戻って来ないお客さんもたくさんいるでしょうし、そうなるとやっぱり新しいことをやらないといけないんですよね。
──お客さんの減少は余程大きなバンドでない限りみなさん抱えている問題ですよね。数字という意味でももちろんですけど、やっぱりライヴとなると目の前に結果があるわけですから、余計に考え込んじゃうバンドも多いんじゃないですか?
久我:そうですねぇ……まぁでも単純に僕は渡邉さんの文章がすごく好きなんですよ。書いてもらうなら絶対渡邉さんがいいなって思っているので。
──あれ?なんか、録音回った途端急に…リップサービスが…
久我:サービストークがねアッハッハ。そんなんじゃないですよ。でも、歌詞の考察は50%くらいかなぁ~当たってるの(笑)。
──あれだけ書いてて半分って、的中率低すぎますね(笑)。
久我:いやぁでも100%ってなるとつまんないじゃないですか。50%くらいが一番良いんですよ。
──そういうもんですかね。でも、あれはただ感じたことを書いているだけなので、正解かどうかは気にならないというか、むしろ分かるわけないと思っているんですよ。いろいろとやってはきたので、それに対して有難いお言葉を頂戴することも極稀にありますけど、実際のところは無力なもんですね。結果的に何か成したかっていうと何も残っていないですから。
久我:ま~たまたご謙遜を~。
いやぁもうそのまんま、細かいことは気にしなくていいんじゃないですか?
──うーん、気にしているというより「むなしいなぁ」って感じですかね。ぼんやり。たまにですけど。
久我:あ、確かにね。虚しいみたいなのはありますね。あるわ。僕だと作曲しているときに「コォレはすごい良い曲!」っていうのがあったとしても、なんとなくフワンと終わっちゃうこともありますし。あらぁって。これ絶対よかったんだけどなぁって。そんな感じで思い通りにいかなかったものは多々ありますね。
──それでいうと、久我さんが最近「満足いく曲が出来ない」って、スランプのお話をされていたじゃないですか。そこから【原点たる様】という3本のライヴを発表されましたよね(収録時は開催前)。
 オール日曜 粋な計らい
オール日曜 粋な計らい──この公演は、なにも古い曲をたくさんやるという意味での原点回帰ではなくて、まだリリースもしていない出来立ての新曲を続々披露して、ライヴでどんどんブラッシュアップしていく。そういう活動の在り方を「原点」と呼んでいるのよっていう。
久我:そうですそうです。
──でも、私は根本から疑っちゃうんですよ。「本当かな?」って。
久我:ほお。
──っていうのも、久我さんが「良くない」とおっしゃっているだけで、多分私を含め、ファンの方がその曲たちを聴いたら「うわぁめっちゃかっこいい!」ってなると思うんですよね。
久我:なーんないなんない!いーやならないですよ。
──いいえ、なります。
久我:ならないならない絶対ならない!!
──なりますって!!
あとこれは個人的な話になっちゃうんですけど、文章とか、最近だと動画を作っているときによく思うんですよ。自分なりにこだわって何度も何度も修正を繰り返している部分なんて、ご覧になっている方からすると、まじどうでもいいことなんだろうなって。細かいことですけど、助詞ひとつとっても「ここは”に”じゃなくて”の”の方がいいかな」とか「この話題に移るときはあと1秒空けた方がいいかな」とか、そういうので結構悩んで時間を使っちゃうんですね。私程度ですらそんなことで迷うんですから、それが対大勢に聴いてもらう作品となるとより深刻だと思うんです。歌詞には音数という制限がありますし、タイム感でいうと「この曲からこの曲へ行くときには2秒の余韻が欲しい。いや、1.5秒かな」とか「むしろ間髪入れずにダーンッとなだれ込んだ方が良いんじゃ?」みたいな。
久我:あーありますねありますあります。
──そこでなんかこの…(久我さんがこちらに手のひらを向ける)
??
クションッ!!
久我:すみません花粉症で。
──(本物だ…)「ここのギターのニュアンスはもうちょっとこうした方がいい」って何十回何百回と録り直すこともあるかと思うんですけど、じゃあそれを出したときにそのこだわりに気付いてもらえるかっていうと、決してそうではないじゃないですか。
久我:そりゃあそうですよー。だって、例えば何かの曲で「ここのブレスを」ってこだわっても、まぁ気になる人は気になるでしょうけど、本当に細かい部分に関しては多分誰も気にしてないだろうし。そういうもんですよ。でも、今回「満足いかない」って言ってるのはニュアンスじゃなくて曲ですもん。曲はダメなもんはダメですよ本当に。どうしようもないですよ(笑)。
──いや、でも絶対良い曲ですよそれ。
久我:絶対だめ!!
でも確かにねぇ、ちょっとそこのズレは面倒くさいところで、曲を作ってくれているメンバーに「何かすごいの頂戴よ!」って求めて、実際に曲を持ってきてもらっても、やっぱり自分的につまんない曲だと「う~ん」ってなっちゃうんですよね。当たり前のことでもあるとは思うんですけど。
──メンバーさんごとに好みもあるでしょうからね…
ただ、「面白い曲」「今までになかった曲」っていう話になると、私は小林さんがLIPHLICHに加入されたことってすごく大きいと思うんですよ。
久我:うん、そうですね。
 ギャグに反して作曲ではスベり知らずなスーパードラマー
ギャグに反して作曲ではスベり知らずなスーパードラマー久我さんは常に変化を求められる方なので、こういうことを言われるのはちょっと心外かもしれないんですけど、LIPHLICHの音楽の基盤は間違いなく久我さんが作ってこられたものじゃないですか。
久我:そうですね。
──なので、私は久我さんの曲を聴くと「あぁLIPHLICHだなぁ。やっぱいいなぁ」って思うんですね。
久我:うんうん。
──ただ、小林さんが作る曲って結構飛び道具的というかびっくり箱で、例えば『三原色ダダ』とか『メランコリー』とか『マジシャンエイボン』もそうですけど、どの曲にも「リフリッチはこういう感じ」という印象をひっくり返すくらいのパワーがあると思うんです。なので、久我さんが変わらず礎としてLIPHLICHの根底の部分を深化させている間に、そこから別方向に遠く伸びた枝葉の部分で小林さんの曲がバンドの間口を広げていっている。同時進行でそれが出来ることって本当に強いなと思うんですよ。新井さんの『夜間避行』もLIPHLICHを象徴する一曲ですし、竹田さんもMASK時代にバンバン作曲されていましたから、4人が4人とも攻撃態勢に入れるバンドじゃないですか。その4つが今後どんどん混ざっていったら…
久我:おもしろそうですよねぇ。
──はい。スランプっておっしゃいますけど、そもそもが以前のリリースペースが異常だったと思うんですよ。「今のLIPHLICH、ちょっと止まっちゃってるのかな?」と思われている方もいるかもしれないですけど、その感覚が一番強いのってむしろ今までのLIPHLICHを知っている方だと思うんですね。でも、それは相対的なものに過ぎないというか。だって、全てが新曲のフルアルバムを年間で2枚出して、その付近でミニアルバムとかシングルもじゃんじゃん出されていたじゃないですか。どう考えても異常ですよ。
久我:たしかにそっか~(笑)。
──念のために伺いたいんですけど、あの時期の楽曲たちは、久我さんのなかで「これは最高だ」と思って出されていたんですよね?
久我:もちろんそうですね。
──(良かったぁ)あの頃の、ファンがLIPHLICHに振り回されまくってる様は凄まじかったですよ。私なんかは特にトロいので、「いやいやまだこのアルバム楽しんでる真っ最中なのにもう次出すの?しかもまたアルバム?しかもまた全新曲?」ってワタワタしていましたもん。一曲一曲が抜群に格好良いし何より濃いもんだから、しばらくはこれをずっと聴いていたいのに、気付けば全く姿形を変えた新アー写が公開されている。それもその状態が何年も続いたわけじゃないですか。気遣い知らずなわんこそば屋みたいなもんですよ。「よく碗を見ろよ!まだ食ってんぞ!」っていう。
久我:ウッハッハ!たしかになぁ~。2016、2017あたりはそうでしたよね。
──はい。あと、私は今のLIPHLICHの曲を聴いていると、えらいダイナミックになったな~っていう印象を受けるんですね。大分勝手なイメージですけど、歌録りが早いんじゃないかなって。敢えての丁寧すぎない歌唱というか、「詩のメッセージを伝える」というより「音としたときの言葉のニュアンス」を大切にされているような。
久我:あぁ~たしかにたしかに。早い、確かにレコーディングは早いですね。
──良い意味での荒さがそのまま活きていて、「これでオッケー!」みたいな明快さが伝わってくるんですね。一ファンの私からすると、そこも変化のひとつだったんです。だから、そういう意味でも「あぁいつものLIPHLICHだな」って思うことが未だにないですし、「まだまだこの一枚を聴いていたい」って素直に思うんですね。なので、リリース期間が多少空いても待ちくたびれた感覚にはならないんですよ。だって、『SMELL STAR〜ケレン気関車 外伝〜』のリリース発表からリリースまでの長さったら半端じゃなかったじゃないですか(笑)。
久我:あぁ『SMELL STAR』は本っ当にもうどうでもいいですね(笑)。
──なんてことを(笑)!
(久我さん、ずっと笑ってる)
──待つのって楽しいもんですよ。それこそ【SKAM LIFE’S IS DEAD】の発表時に公開されたティザーっぽい映像の最後に、ほんんんんの数秒だけ『特例Z』が流れたじゃないですか。私、あの数秒を繰り返し聴きまくった方がかなりの数いるんじゃないかなって思うんですね。LIPHLICHの曲には、一瞬で人を惹きつける魅力がありますから。
久我:ですかねぇ。あれはちょっと時間かかりすぎましたからね(笑)。
──【SKAM LIFE’S IS DEAD】の終演後に「LIPHLICH TIMES」というかさばる紙を配布させていただいたんですけど、その紙面で初めて『SMELL STAR(『特例Z』が収録されているアルバム)』のリリースをファンの方が知るかたちになっていたじゃないですか。でも、待てど暮らせどリリースがないまま大分月日が流れて、「本当にでるのか?」と。なんか嘘つきの片棒担がされた気分になっちゃって(笑)。
久我:いろいろあったんでねぇ(笑)。
──あんなにも不安定な期間を変わらない気持ちで待ち続けられたファンの想いの強さもすごいと思うんですね。あのときのことを思い浮かべると、より一層「この企画はどうしても実現させたい」って強く思うんです。【解体新悟】を提案させていただく最も大きな動機として、「久我さんにはもっと表に出てほしい」という願いがあるんですよ。ただのエゴっちゃエゴですけど、「久我さんの言葉を久我さんの声でもっと聞きたい」って、ファンの方もそう思っているはずだという確信みたいなものもあって。この後の企画概要でもお話することなんですけど、LIPHLICHのファンで久我さんの声が好きじゃない方なんてまずいないじゃないですか。
久我:いやぁ~それはできればそうであってほしいですよね(笑)。
──もう絶対です。それはなにも歌声だけの話じゃなくて、こうしてお話されている地声もすごく愛されている方だと思うんですね。でも、生憎世の中に久我さんの声が少なすぎるんですよ。その身共々隠居しすぎというか(笑)。
久我:そうかなぁ~。じゃあASMRでも始めましょうか?
──いいですね。『マズロウマンション』の回あたりで一本やってみましょう。
久我:なんでマズロウマンション(笑)。
──これまではなかったものですから意識こそしていなかったにしても、こうして記事であったり、今後作りたいと思っている音声コンテンツに触れていただいたときに「あぁこういうの欲しかったんだな」って、そう思ってもらえるものを作りたいんです。
久我:うん、いいですね。
──まぁでも私が一番恐れていることを先に言っちゃうと、久我さんが企画自体に飽きちゃうことなんですよね(笑)。今は「あ、これ楽しいね。やろうよ」っていう雰囲気を出してくださっていますけど、ファン全員に浸透しているくらいの飽き性じゃないですか。3回目ぐらいで「ちょっと面倒くさいな」ってなられるのが怖いったらないですね。
久我:あはは。いやぁこれはもうそんなことないですよ(笑)。
──どうですかねぇ(眉唾)?
って疑っちゃうのにも理由があって…以前にYouTubeで新井さんとトーク配信をされていましたよね?
久我:あぁネットラジオみたいなやつですね。やりました。
──あのときも「これ楽しいね。いつまでも喋れちゃうね。引き続きやっていこうよ」と言いつつ、舌の根も乾かないうちに「でも、俺はレギュラーじゃないんだよね?」って確認されていたじゃないですか。「毎回出るってなるとちょっとアレだな」感ダダ漏れの(笑)。私はそれがすごく面白かったんですけど、いざ自分が相手役にさせていただくとなると話は変わってきますよね(笑)。
久我:いやぁ~あれはあれって感じですよ。続けていっても特に喋ることがなくなって、ただの日常会話になっちゃいますからね。
──それでも良いと思うんですよね。ファンの方は喜ばれますよ。
LIPHLICHって一時期、終演後のメンバー写真をSNSにあげなくなったじゃないですか。あの期間も多分ファンの方は「写真欲しいな」って思われていたはずなんです。でも、最近になってライヴの写真であったり、なんなら映像まで出されたりしているので、いろんな事情があって長期的にライヴに参加できない方や、「その日のライヴはどうしても行けなかった」という方からしてもとても嬉しいと思うんですね。
久我:それはもう本当に。そういう方たちに見てほしいからやっていますね。
──やっぱり絶対に来られない理由がある方もいらっしゃるじゃないですか。特にLIPHLICHのファンの方々って皆さん大人なので、コロナとは関係なく……これは自分の話になっちゃうんですけど、親が60代、70代になってきて、これから先のことを考えなきゃいけないなって思う時間が増えたりとか。あとはお子さんがいらっしゃったり、お仕事の時期的に「今感染するわけにはいかない」と警戒されている方もいる。本来そんな権利なんてないんですけど、会社から禁止されている方もいらっしゃるくらいですからね。でも、シーンのファンとして本当に嫌だなぁと思うのは、行きたいときに行けない状態が続いてしまうと、音楽の質であったりバンドへの想いの大きさとは関係ないところで冷めてきてしまうものがあるってことで。
久我:はいはい。あると思いますよね。それは。
──習慣として「行かなかったら行かないで平気になっちゃう」といいますか、そこが今一番の敵なんじゃないかなって。
久我:それはもうしょうがないですよ。やっぱりあくまでも音楽は娯楽ですからね。「それが生き甲斐」って夢中になってくれる方もいるとは思うんですけど、必ずしもそれが永遠に続くっていうものではないので。みんなそれぞれの人生がありますからね。それにそういうことを考えると、いろんなことが虚しくなっちゃうと思うんですよ。自分の思うような結果が出ないとか、ファンの人が離れちゃうとか。実際にそういうので嫌になる人も多いと思うんですけど、これを考え出すとキリがないので、俺は考えないようにしているんですよ。
──「考えない」っていうのは、自然とそういう考えになってきた感じですか?それとも意識的にですか?
久我:あぁどっちかなぁ~……それよりもなんかねぇ、もう常にずーっと自分のことで一杯一杯なんですよ(笑)。「自分の中に興味がある」というか。それはバンド自体のことですけどね。
今は確かにライヴだけをやっている状態ですけど、2020年には『ケレン気関車』と『ケレン気関車 弐』を出して…『SMELL STAR』に関しては本当にもう賞味期限切れの腐ったものというか(笑)。それも今とは違って前の事務所から売ったもので、そのときはちゃんと(盤を)作ってすらいなかったみたいな状態だったので、「なんとか処理しなきゃ、この残飯を」って(笑)。
──ざ、残飯ッ(笑)!
(自らの発言がツボに入ったのか、久我さんしばし笑いの尾を引く)
久我:こういうことを言うと曲が好きな人には申し訳ないですよね。しかもこれが自分の曲だけだったら良いんだけど、メンバーの曲もあるわけで、こういう言い方だとメンバーも良い気しないじゃないですか。例えが悪かったですね(笑)。残飯はやめよう。
──いやぁ私はかなり好きでしたけどね。あの残飯。
久我:(笑)昔作った状態のままであまりに出さなすぎると、「もうちょっとこう出来たのになぁ」っていうのが絶対にあるので。で、なんとかそういう問題を越えてー……うーん、やっぱり今はこの状況に飽きているんでしょうね。だから、なんとか自分を追いつめて追いつめて、この【原点たる様】で更に追いつめて曲を作ろうという状態です。若干出来てはきたんですよ。「いい感じ・かなぁ~」っていう曲が。ようやく。
──おぉそれは良かったです。ちなみになんですけど、今の久我さんが求める曲ってどういうものなんですか?今までLIPHLICHでは全く作ってこなかったタイプの曲なのか、「LIPHLICHだな」と思わせるものでありながら、それをさらに昇華させた様な曲なのか。
久我:うーんどうだろう……
──それこそ私は『FLEURET』を初めて聴いたときにびっくりしたんですよ。「これLIPHLICHの曲なんだ!」って。詩のメッセージが超真っ直ぐじゃないですか。あのドーンッと真っ向勝負な感じが新しくて、「メジャーデビューシングルじゃん!」って飛び起きるくらいの衝撃があったんですね。
久我:そうそうそう、だから、ああいう曲って誰でも出来るというか、「どこのバンドがやっててもいいじゃん」っていうのかな。「今ならこういうのを歌っても心情的には良いかなぁ」って感じですか。だからこう、あんまり言い方は良くないんですけど、メロディーとか歌詞についてはクソみたいなもんだと思っているんですよ。
──使えないですよこれ(笑)。
久我:(笑)た・だ!あれが意外とグッとくるような年齢になったのかなぁって。本来はああいうのをやりたくて音楽をやっているわけではないので。自分の中ではこっぱずかしいけど、出来ちゃったしいいかと。でも、曲自体に関しては世の中的に本当に価値のない曲だと思うんですよね。あーーって、言い方悪いなぁ(笑)。
──ははは
久我:好きでいてくれる人もいるから価値はある。それは良いんですけど…
──久我さん久我さん、あの歌で泣いてるファンもたくさんいますよ(神妙)。
久我:ちがうちがうちがうそうじゃなくて(笑)。言葉が悪かったですけど、『FLEURET』は演奏していても気持ち良いですし、あれはあれで良いんですよ。ただ、サウンドとメロディーはありふれているので、そこまでっていうものでもないんですね。
──となると、やっぱりLIPHLICH的に新しければ何でも良いというわけではなさそうですね。
久我:そうですね。あと、シングルを作るときには「まぁLIPHLICHっぽいのも入れてー新しいものも入れてー」みたいなことを常に考えてバランスをとる様にしているんですけど、そこらへんが今分かんなくなっちゃってるんでしょうね。
──次の戦略が明確じゃないっていう?
久我:そうです。さてどうしようかと。だから「今求めているもの」といっても、LIPHLICHっぽいものも大事な気もするし、新しいものも大事な気もするしー…あと、シングルを出そうってなったときはやっぱり曲数が限られるから、その辺を狙って作るようになっちゃって、逆になにも出来なくなったんですよ。
──決め打ちしようとしたら、かえって的が見えなくなってしまったみたいな感じですかね?
久我:そうそうまさに。(シングルのなかで)この役の曲、この役の曲、この役の曲っていう風に考えてやっちゃうと、「あぁ~これは作ったけど、(同じ役割の曲でいうと)『飽聴のデリカテッセン』の方が明らかに良いなぁ」とか。だから、曲数の制限とかはなにも考えずに「原点たる」っていう感じで、「とりあえずライヴでなんでもいいからやっちゃえばいいじゃん」っていうところですね。
──それはやっぱりLIPHLICHからするとファンの方からの反応は関係ない感じですか?例えばですけど、久我さんご自身が「そうでもないな」って思うような曲でもファンの反応が良ければそれでいこうっていうタイプのバンドではない気がするんですが。
久我:あぁーファンの反応は関係ないですね(笑)。他のバンドの方がどういう気持ちで「手応え」と言っているのかは分からないですけど、うちは盛り上がるか盛り上がらないかって話ではなくて、一回音で出してみて……うーん……あぁもしかしたら「ライヴで」っていうのは関係ないのかもしれないな。そこで判断するというより、ある程度出来上がった上で、練習?実験?ライヴで練習というか、公開実験みたいな。ひとまず試してみるっていう感じなので、観てくれている人の反応っていうのは本当になんでもいいです。
──なるほど。じゃあファンの方がワッとなる様な曲でもそれが未来の残飯となる可能性もあると。「残飯食って泣け」と。
久我:ウハハハ。そんなこと言ってないですよ(笑)。いやぁでももうちょっと言い方ありましたよねぇ。拙いなぁ。
──ファンの方には思い入れがありますからね。でも、久我さんのキャラクターが出ていて、みなさん面白がってくださるんじゃないかなって思いますよ。
久我:はい。むしろそういうタイプだって思ってもらいたいですね。「昔の曲はどうでもいい」っていうことは割とずっと言ってきた様な気がするんですけど。
──あぁーそれはそうですよね。でもやっぱり書かれている歌詞とかバンドのイメージ的に久我さんが作品に対してすごく神経質なアーティストだと思われている方も多い気がします。実際私もそうでしたし。
とはいえですよ。今からすれば昔でも、LIPHLICHの登場って当時の私にとって本当に鮮烈だったんです。私は、『6 Degrees of Separation』が出るちょっと前あたり(2011年)からZEAL LINKで働き始めたんですね。で、どこのCDショップでもそうだと思うんですけど、面接で好きなバンドとか注目しているバンドについて聞かれるんですよ。そのときにLIPHLICHの名前を真っ先にあげたんです。でも、まだ流通しているCDが一枚もなかったので…
久我:「リフリッチ?」みたいな感じだったんでしたよね?
──はい。「リフ?ん?」って。その状態からリリースを重ねるごとにどんどんお客さんが増えていって、『SKAM LIFE』のときにイベントスペースのマックスキャパをびっしり埋めたじゃないですか。しかも2部制で。あれって年間で10バンドもいないくらいの偉業なんですよ。そうやってLIPHLICHが0から駆け上がっていく過程を近くで見られたのは本当に幸せでしたねぇ…月並みですけど、やっぱり”知られる”っていいですよね。
久我:良いですね。分かります。僕も「知ってんだー」って驚くことがあるんですよ。この間もツアーで福岡へ行ったときにプライベートでも仕事でも付き合いのある友達と会ったんですけど、その友達が別の飲みの席で僕の話をしてくれたらしくて、そこで同席していた人たちから「LIPHLICH知ってるー!」って言われたみたいなんですね。それを聞いて嬉しいなぁって。
──いやー、でも本当にアレなんですよ。ご本人を前にして偉そうに言うことじゃないんですけど、LIPHLICHはもっと大きくなるはずなんですよ。もうなくなっちゃいましたけどAREAとか、今でいうと池袋EDGEで頻繁にライヴをされているじゃないですか。私もCD屋時代には公私ともに大変お世話になったライヴハウスですし、スタッフさんのシーンに対する熱も大好きなんですけど、LIPHLICHの音を鳴らすとなるとやっぱり物理的に小さすぎるんですよね。LIPHLICHのパフォーマンスって、音だけをとっても凄まじい広がりと高さがあるじゃないですか。それをキャパ300付近でってなると場が一瞬で飽和しちゃうというか、濃すぎてなにか別のものになってしまう様な気がしちゃうんです。ポテンシャルを発揮しきれないといいますか…
久我:いやーだからそうなので、これはもう頑張って人気出すしかないですねぇ(笑)。
──こんな情勢になる前は、劇場公演を毎年開催されていたじゃないですか。あれがもうどれもこれも本っ当に素晴らしくて。
久我:そうですね。だからなぁ…できたらいいなぁ…今年、ホールやっちゃおうかな。
──是非やっていただきたいですね。
ライヴハウスに慣れているファンがホール公演に向かうときの気持ちって本当に特別で、めちゃくちゃテンション上がるんですよ。なんかこう「バンドが連れてきてくれた!」って気持ちになるんです。ライヴハウスでワチャワチャするのが好きという方も会場に入った瞬間は「わぁ素敵」ってなるはずで、LIPHLICHを愛している方からすればより一層その気持ちも強いんじゃないかなって思うんですね。綺麗な会場にフカフカの椅子がズラーッと並んでいる。天井も高くて、ステージも広い。舞台の大きさに比例して、そこを持ち場としたときのLIPHLICHは魅力を増しますから。なので、これはライヴハウスやLIPHLICHに対しても大変失礼な言い方になるんですけど、小箱での公演が発表されると「ここでやるのか…」ってつい思ってしまうんですよね。
久我:いやぁそうですよね。出来れば毎月ホールでやりたいんですけどね。
──そういえば、(ホールワンマンの)予定があったみたいな話もされていましたよね?
久我:あ、去年ですね。去年の年末らへんに押さえていたんですけどね。いろいろあって、ダメになりました。だからそうだなぁ…そういう自分たちに会える様にホールを作ってしまうっていうのも…
──SEKAI NO OWARIみたいな感じですか?彼らは自分たちでライヴハウスを作ったじゃないですか。
久我:え?そうなんですか?
──はい。駆け出しのときに自分たちでテナントとってライヴハウスに改装して、そこでライヴをしていたみたいですよ。
久我:ほぉ~賢い。そういうのもありかなぁって思っているんですよ。ちょっと前まで椎名林檎さんが「キャバレー作りたいわ」って言っていたので、作って作って~♪みたいな(笑)。規模感的にもすごい良さそうだったので期待していたんですけどね。
──やっぱり「会場」って、なにかがありますよね。それが同じリリースに伴うツアーであっても演奏される曲が同じであったとしても感じ方が変わったり、それこそ地域ごとに盛り上がりの質感が違ったりするじゃないですか。
久我:そうですね。やる方としてはライヴハウスも好きなんですけどね。やっぱりやりやすい・やりにくいっていうのはありますよ。でも一番は相性かな。相性が良いところ・悪いところっていう。でもそうか、ホールねぇ……今年、やってみようかな。
──もう是非是非。ホールで新曲が聴けるっていうのも素敵ですね。といっても、今回は敢えて新曲から一番遠い古の作品からバンドの歴史を辿っていくという企画のご相談に伺っているんですけど(笑)。
久我:あぁそうでした(笑)。
──CDショップで働いていた頃から、私は旧譜を売るのが大好きなんですよね。
久我:うん。いろいろやってくださっていましたよね。
──えぇ馬鹿みたいに(笑)。LIPHLICHをはじめ、100以上のバンドのコーナーを血眼で作っていたんですけど、あのときの気持ちは退職してからもずっと残っているんです。単純に「旧譜を過去のものとして扱いたくない」っていうのもありますし、あとはまだファンの方には馴染んでいないもの、なんなら一度も聴いたことのない新曲について触れることにはあまり乗り気になれないんですね。それをしてしまうと変な先入観を与えてしまう気がしてしまって。なので、ある程度浸透しきったときにその作品について書いてみるっていうのが自然で良いなって。だから、今回の様な企画をやってみたいとはずっと前から考えていたんですよ。
でも、久我さん脳内大解剖計画「解体新悟」の開催は僕の夢ですので、もう少し賢くなって「今なら出来るナ」と思える様になったら、というより第三者から求められる様になった暁には三時間スペシャルでお送りしたいなぁと思います。まぁアーティストは星みたいなものなので近付きゃしないんだけどネ。
— ap.kani (@ap_kani) January 4, 2016
6年越しに叶った
久我:なるほどねぇ。あぁでも今言われたことはまさにそうですね。最初にそういうものがあっちゃうと、それの固定観念というかね。それで聴いちゃうってなりますよね。
──はい。久我さんはお忙しい方なので、この企画もそんなに頻繁に出来るかっていうと難しいと思うんですよ。しかも、作品ごとにお話を伺うという流れになるので、次に出る新曲についてお聞きするのが何年先になるかも分からない。もう欲望だけをぶつければ、今の段階で『星の歯車』とか『キーストーン』とか『一輪』の話をしたくてしょうがないんですけど、ルールに従って順々にってなると、2年先くらいになっちゃうという(笑)。
久我:ハッハ
──あとは、WEBメディアや雑誌に掲載される形式での新譜インタビューを見ると、「本当にお客さんはこういうものを求めているのかな?」って疑っちゃう部分が昔からあって。なんかこう「要約された回答」を常に求められる就職面接みたいな印象を受けるんですね。やりとりがある程度パターン化されていて、「こう聞かれるだろうからこう返す」っていうのがありありと見えるというか…
久我:なるほどねぇ。
──質問として「聴きどころは?」なんて最悪ですよ。「一から十まで聴いてる時間(文字数)ないからサビだけ聴かして!」って言ってるようなものですから。なので、面接みたいな一問一答形式のインタビューだけはどうしても避けたい、というか私には能力的に出来ないんです。それに付随する現在の心境や背景も聞きたいという欲を抑えられないので。ってなると、自然とそこから離れた「まとまっていないもの、要約されていないもの」になるんですね。つまりは超長い音声や記事にな…
久我:(カットイン)ん?ん?あれ?なんかさっきまで(録音前)より言い方が大分丁寧になってませんか?もっとボロクソに言ってた様な気がするんだけどなぁ~…あんれぇ~…
──久我さん、TPOってご存じですか?
久我:ん?んん?聞き間違えかなぁ~(不敵笑)。
──……続けますね。えーっとなんだっけ(動揺)、あぁつまりはそういう「インタビューの作法」みたいなものがあまり好きになれないんです。結局何にも迫れないまま終わっちゃうので、LIPHLICHには合わないだろうなとも思っていて。特に久我さんの歌詞って、すごく抽象的じゃないですか。
久我:そうですね(疑惑のニヤつき継続中)。
──「このことについて歌っています、さぁどうぞ」じゃなくて、受け手自身が「これってこういうことなのかな?」って、想像しながら楽しめる詩を書かれる方だと思うんですよ。だから、先立って解説するのはナンセンスだと思っているんですね。それに久我さんの歌って歌詞以外にも「声が好き」「リズムが好き」「詩を音(おん)としたときの気持ち良さが好き」みたいにいろんな楽しみ方が出来るじゃないですか。それこそ「歌詞はそこまで重要視しない」という方もおられますよね。
久我:うんうん。
──私も「歌詞をすごく大切に思ってるんだね」みたいなことを言われることが多いんですけど、実際はそうでもないんですよ。「紹介したいな」って思ったとき以外で歌詞カードに目を通すことなんてほぼないですし。ただ、自分が好きになる曲を改めて思い返してみると、やっぱり詩の良さに行きつくんですよね。自然と。
久我:なるほどなぁ。でも僕はどっちかっていうと、渡邉さんの文章を読みたいっていうタイプなので、聴いたまま好きに書いてもらって、それを読んで「へぇ~~」って楽しんでいけたらいいかなって思っていたんですけど(笑)。
──あらぁ…そうなると企画が台無しに(笑)。【解体新悟】は、私が勝手に書くというよりも、今まで書いてきた様なことをお話して、それについて久我さんに返していただいて、そこからどんどん話を広げていくという流れになるので、むしろ真逆ですね。労働です労働(笑)。
でも、それより大問題なのが、企画書を作らせていただいて、久我さんにこれから趣旨を聞いてもらおうっていう段階に立った今、死ぬほどこっぱずかしいってことなんですよ。
久我:アッハハ
──なので、台本を作ってなんとなくそれに沿って~っていうよりも、今みたくフリーな感じでお話しする方が良いなって。
久我:そうですね。それが良いですよ。
──決められたもの通りってなるときついですよね。私は根が不真面目なので、そうするとどうしても上手くいかない。
久我:ほぉ。不真面目。そうなんだ。
──はい。で、めちゃくちゃ失礼ですけど、先ほどまでずっとお話をさせていただいて思ったのが、久我さんもおそらくそうなんじゃないかなぁって…うっすら思っていたり…
久我:いやぁ~僕は真面目ですよ~真面目ですよぉ~(⤴)。
──なんというかこう、決められたタスクを決められたルールのなか、決められたペースでどんどんこなしていけるタイプではなさそうな…
久我:あぁ~それはないですね。それは出来ない(笑)。
──これも私の話になっちゃうんですけど、物を作るときでもとにっかく腰が重いんですね。やってるときは夢中になって寝るのも忘れてガーッと入っていけるんですけど、「やりはじめる」ってところまでに全く行きつけないんです。「あと一時間したらやろ~やっぱ二時間後にしよ~もう明日にしよ~」で、グゥ(寝る)みたいな。
久我:あぁぁあはいはいはい。なりますね~ありますね~往々にしてありますね~それ(笑)。
──久我さん、日本ではそれを「不真面目」って言うんですよ(笑)。
久我:そうかー不真面目。おかしいな、真面目で通ってるんだけどなぁ(笑)。
──自分で言うのもあれですけど、不真面目な奴がここまで緊張するっていうのもおかしな話なんですよね。拙いもんですけど、ヴィジュアル系にまつわる文章を書くようになってからもう15年以上経ちますし、なんなら専門店でまで働いていたのにアーティストとの関わりだけはずっと避けてきたので、実際に今日久我さんとお会いして自分がどういう気持ちになるのかが全然想像出来なかったんですよ。で、もう分かるんです、今の久我さんが思われていることが。「お前、そんなに喋る奴だったっけ?」って。
久我:そうそうそう(笑)!あんなに会話を拒否られていたのに。
──人聞き悪いですよ(笑)。畏怖です畏怖。尊敬故です。
私は元々人見知りとも緊張とも無縁な性格なので、昨日までは「まぁなんとかなるかな」って思っていたんですけど、蓋を開けてみたら気絶するんじゃないかってくらい緊張している今があって、「うわぁ緊張してる自分ってこんな感じかぁ」ってちょっと引いてるくらいなんですね。ここが韓国だったら今日をもって「キン・チョウスル」に改名していたところですよ。
久我:フハハ。もぉ~そんなに緊張しちゃってねぇ。歳も変わらないのに~。ほとんどタメじゃないですか〜。
──LIPHLICHを好きになってから今日に至るまでに12年掛かっていますから無理もないですよ。LIPHLICHを知った頃は酒屋で始発から終電まで働いて、ぐったりしながら毎晩ブログを書いて寝ての繰り返しだったんですね。好きな音楽も固定化してきて、それでもまぁ満足はしていて、でも心のどこかに悶々としたものを抱えていて…ってときに土足でガァァアンッとやってきたのがLIPHLICHで。
久我:嬉しいですねぇ。
──この話は私と同じ世代(1985年生)の方に共感していただけるんじゃないかなって思うんですけど、このぐらいの年齢までずっとヴィジュアル系を聴いていると、新しく生まれたバンドのなかに一人も知っているメンバーがいないってことがほぼないんですよ。
久我:あーなるほど。
──当時ですらその状態だったので、LIPHLICHを初めて観たときに「この人たちなんなの!!??」って度肝を抜かれたんです。で、当然家に帰って調べるわけですよ。「リフリッチ…ライヴでは分からなかったけど、名前を見れば元のバンドが分かるかもしれない」って。でも、結果は「くがしんご?誰?きくちあきと?誰?しんどうわたる?誰?まるやまえいき?ぜんぶ、ダレ!!」みたいな。
久我:ハッハッハ
──なんなら、当時のアーティスト写真を見たときに「なんで3人しかいないのに名前が4つあるんだろう?」って思ってたくらいですからね。渉さんが影の男過ぎて。
 久我さんの左にいます
久我さんの左にいます久我:そうでしたそうでした(笑)。
そっかぁ、そうだよなぁ。うちはパッと出だからなぁ。
──そういうのもあって、誰も知らないバンドを好きになれたことが本当に嬉しかったんですよ。奇跡みたいなものでした。
久我:新発見!みたいなことですよね。
──そうですそうです。しかもそれがめちゃくちゃ格好良いもんですから、「一体これからどうなっていくんだろう…」ってあのワクワク感ったらすごかったんですよ。で、今後そういうバンドが他に出てくるのかなって思ったときに、正直言うともう出てこないんじゃないかなって今は思うんです。悲しいですけどね。
久我:出てきてほしいですけどねぇ~。あ、でもnurié好きですよnurié。格好良いと思います。
──おぉnurié。突き抜けてますよね。あ、そういえばnuriéもですけど、最近楽曲に鍵盤を使われるバンドが増えてきましたよね。最近のChantyもそうですけど、バンド楽器以外の音も映えている音楽がどんどん出てくるなぁって。それこそLIPHLICHでいってもあらゆる楽器を取り入れているじゃないですか。
久我:あぁそうですね。
──私はねぇ、『ケレン気関車』とか『慰めにBET』とか、管楽器を入れて生で聴きたいんですよライヴで。それもひとりふたりではなくて楽団従えてワーーーッと。もちろん同期でも格好良いんですけど、あの音が生でLIPHLICHと共鳴するのを想像すると「わぁ」ってなっちゃいますね。
久我:確かにねぇ。じゃあそれはいつかのホールのときにでも。やろっかなぁ~。
──わぁ期待しています。ホールといえば、THEATRE1010での劇場公演も演奏中にサンドアートがリアルタイムでスクリーンに流れていたじゃないですか。あの演出も画期的すぎて痺れました。
久我:あぁーあれも良かったですねぇ。
──LIPHLICHって予想の範疇を超えるどころか、訳分かんないところから奇襲を仕掛けてくるじゃないですか。それこそさっきもおっしゃっていた「盛り上がれる」「楽しい」だけのライヴではない。なんなら客席を凍り付かせるような演出も得意ですよね。リキッドルームでの【VLACK APRIL#2】も冷や汗もんでしたから。あんなに客席が緊張感で打ちのめされているライヴ観たことないですよ。
 LIPHLICH TIMES 7号でレポったよ
LIPHLICH TIMES 7号でレポったよ久我:そんな感じ…でしたかねぇ~~(回想の旅)……でした、ね。でしたでした!
──つい最近行われたコンセプトワンマンの【暗暗たる様】もですけど、ああいう戦慄系のLIPHLICHが好きで好きでたまらない方も多いと思うんです。観終わった後に一斉にため息をついて、「いやぁすごいもの観ちゃったなぁ…」って深~~い余韻に浸る。そんな歓声不要なライヴも魅力なLIPHLICHにとって、コロナ禍の今ってかえってチャンスなんじゃないかなって思ったりもするんですよね。
久我:あぁそれは自分でも思ってますねぇ(ニンマリ)。
それに限らず、ライヴも本数的にはコンスタントにやっているんですよ。今でも「ライヴに行く」っていうのを選んでくれる方には来ていただいていますけど、やっぱりそれぞれいろんな状況があるでしょうから難しい部分もあって。ただ、そういうときでも例えばバースデーライヴみたいなバンドにとって特別な日とか特別な場所でのライヴってなると、「あ、じゃあ行こうかな」とか「ここは行きたいな」とか、ファンにとってはそういう心情があるじゃないですか。それこそ「一年に一回そういうライヴに行ければ良い」っていう方もいるでしょうし。だから、そういうことを考えても、やっぱり特別な日のひとつとしてホールでもやった方が良いよなぁって、今日お話していて思いました。うん。やりたいな。
──ホールのLIPHLICHは最高ですからね。バンドもファンもやりづらい情勢ですけど、劇場公演となると精神的なハードルが下がることもあるでしょうし、良いこと尽くめな気がします。先ほどの「ライヴ写真や映像はそういう方に宛てたもの」というお話と同じ…っていうと大分おこがましいですけど、この【解体新悟】も離れている間に楽しんでもらえる企画にできたら嬉しいなって思っているんです。あとは、この企画を通して初めてちゃんとLIPHLICHを聴いたという方が出てきてくださった場合、曲を聴いただけでも「これは確かにホールで光るバンドだなぁ」って頷いてもらえる自信もあるんですよね。それくらいに音像と声の広さが桁外れですから。
久我:うんうん。もちろん好みもありますけど、そういうバンドがもっと増えてくれたら良いなぁって思いますね。
──そうですね。ライヴというとスポーツ的な楽しみ方もありますし、むしろロックといえばそっちの認識の方が一般的だとは思うんですよ。ただ、体を動かしていないと充実感を得られないってなると少し話が違ってくるといいますか。これは歳のせいでもあるのか、学生時代なんかはちょっとでもライトな曲とか歌モノが続くと「うわぁ丸くなっちゃったのかなぁ」って、自分の好みから外れたバンドに対して好き勝手言っていましたけど、今になってみたら「あぁー…中島みゆき…いいなぁ~」って(笑)。
久我:うんうん(笑)。良いですよね。確かにゆったりとした曲をやっていて、それがいまいちだったとしたら観ている側としても眠くなっちゃいますもんね。素敵じゃないと。
──久我さんご本人も感じられていることかもしれないんですけど、LIPHLICHがライヴでバラードを演奏しているときの時間って、すごく特別な空気が流れているんですよね。後ろから観ていても「あ、みんなこういうの好きなんだな」ってヒシヒシと伝わってくるんですよ。「あぁバラード始まったわ。ここから聴かせるゾーン突入ね」っていう熱の落ち方がなくて、むしろグッと受け入れ態勢に入るというか。気持ちが。
久我:そうですね。それはやっていても感じますね。
──久我さんの歌も進化しまくってるじゃないですか。あれは本当に素晴らしいですよ。
久我:歌、うまくなったのかなぁ~…
──いや、本当に。歌い上げているときのパワーには毎回驚きますもん。あと、久我さんは声質の部分でもすごく特徴のある方ですけど、それを差し引いても「ここでしか聴けない歌」を常に歌われているなって思うんです。その最上級がライヴであることは言うまでもないんですが、音源でも十分にそれが伝わってくるんですよね。例えば街を歩いていて、どっかのスピーカーから聴いたことのないLIPHLICHの新曲が流れてきたとしても一瞬で「わ!久我さんだ!」って分かるでしょうから。
久我:あぁ~そうなれてたんだ。良かった。自分では分からないんですよね。そうなれていると嬉しいですね。そういうタイプの声の人っているじゃないですか。一発聴いたら分かるっていう。うん、なれてたらいいな。
──十分すぎるくらいだと思います。ちなみにそこでの「らしさ」による葛藤みたいなものはないですか?
久我:ん?
──「LIPHLICHだ」って一瞬で分かられる、いわゆる「LIPHLICHらしさ」っていうのは、変化を求める久我さんにとって邪魔なものにならないのかなって。
久我:あーいや、声はないですね。声はむしろ、それでなければいけないと思っているので。そういう葛藤は声以外の部分です。歌詞と曲、アレンジですね。声はだってどうしようもないから(笑)。
──久我さんって結構いろんなところで「歌を始めた頃は本当に下手だった」っておっしゃってるじゃないですか。
久我:はいはい。
──でも、私は一番最初にファーストアルバムを聴いたときから「この人の歌すごいな」って思ったんですよ。もう仕上がっているというか、表現したいものが明確に見えている印象があったんです。
久我:あぁそうですかねぇ。
──逆にしばらく経ってからリリースされた『マズロウマンション』を今聴くと「(声が)若いなぁ~」って思うんですよ。不思議と。
久我:若いのかなぁ。若いですか?『マズロウマンション』なんて何年聴いてないんだろう(笑)。
──なんにせよ、デビュー作から他のバンドと雰囲気が違いすぎたんですよ。
で、これまた私の勝手な印象話というか、バンドの推移を追ってきて思ったことなんですけど、初めて『SOMETHING WICKED COMES HERE(LIPHLICHのファーストアルバム)』を聴いたときに、すんごい分厚い暗幕が舞台と客席の間に垂らされていて、全然向こう側(LIPHLICH)が見えないっていう映像が浮かんだんですね。音楽こそ聴こえてくるけど、この幕の奥に人がいるのかも町があるのかも、晴れているのかも雨降りなのかも分からない。ただ、なにかしらのいかがわしい行為が向こう側で行われているってことだけは分かる。そんなイメージだったんです。
久我:なるほど、いかがわしい。いいですね。最ッ高の褒め言葉ですね(笑)。
──(笑)それが徐々に、それこそ『Ms.Luminous』が出た頃には、モノクロではあるんですけど、その暗幕が厚手のレースカーテンくらいになっていて、「あ、人がいるんだ。女性なんだ。人生が思うようにいかなくて悩んでんだ。でも自分の非は認めたくないんだ」っていう感情の部分まで見えてきて、次の『MANIC PIXIE』あたりからはフルカラーで「なんかめちゃくちゃキレてる男がいるぞ。しかも気に入らないことに対してすごい剣幕で捲し立ててら」っていう。
久我:ウッフッフッフ
──で、その薄い幕すらも完全にあがりきって、そこで初めて『SOMETHING WICKED COMES HERE』で見世物小屋を管理していた人間が実は見世物そのものだったってことに気付くと。そしたら、そいつが自我を持ち始めて、どんどんスター性を帯びてきて、大分先にはなりますけど『FLEURET』まで時が進んだら、そこにはもう見世物でもなんでもない、完全体の久我新悟のご登場!バァァアアンッ!って感じだったんです。ご本尊!みたいな。なので、私の中で一番LIPHLICHの世界にモヤが掛かっていない状態の作品が『CLUB FLEURET』なんですよ。リアルな人間の歌を聴いている感覚っていうんですかね。
久我:うんうん。そうですね、そうですそうです。やっぱ面白いなぁ。
──で、私は勝手に思うんですよ。久我さんって、バンドが不安定なときには裸の感情を切々と歌って、逆にバンドが安定してくると強烈な悪役の皮を被る天邪鬼なんじゃないかなって。
久我:ほぉ~。
──なんかこう、バンドが上手く回り続けることを手放しに善しとはしていないというか、その状態を「ぬるい」と思ってしまわれる様な…うーん、例えば今でいうとようやく竹田さんという素晴らしいベーシストが見つかって、紆余曲折ありながらも新曲を出して、ライヴも出来てっていう状況があるじゃないですか。「これなら長く続けていけそうだぞ」って。当然それは喜ばしいことで、ファンとしても嬉しい限りなんですけど、今の様ないわゆる「安定期」が続いていくと、なにかのきっかけで急に「ぶっ壊してやる!」みたいな久我さんが現れる様な…
久我:あああああ!!今なってます!!まさに。なってますねぇ~なってます(笑)。見抜かれてるなぁ。そうそうそう。今のままは良くないと思っていますね。攻めないとって。
──LIPHLICHの曲にはそういうヒリヒリした感情も表れていると思うんですよね。結構聴いていて精神的にくるというか…
久我:くる曲というと…それは…
一同:嫌いじゃないが好きではない
久我:あははは。渡邉さんが大っ嫌いな曲ですね。
──もう大っ嫌いですね。世の中に存在する曲の中で一番嫌いです(笑)。そもそもの話になりますけど、LIPHLICHの曲って共感できるものじゃないじゃないですか。
久我:そうですね(笑)。
──「私もこういう気持ちになったことある!」とか、「私のこと歌ってくれてるみたい!」とか、悲しいくらいないんですよそういうのが。
久我:ですねですね。
──だというのに!ですよ。よりにもよって、あんなにも最悪な曲が自分の中にあるものと全く同じだったっていう。
久我:ウッハッハ
──悲しいったらないですよ。私は久我さんに憧れているのにこんなところでしか共感できないのかって。もっと『FLEURET』みたいな勇敢な曲でこの感動を味わいたかったなぁ。それが例え残飯でも。
久我:ハッハッハ
──汎用的な、というか、通じやすいラブソングも一曲もないじゃないですか。「あんたLINEは既読無視するくせにSNSは更新するのね~♪」みたいな。極端ですけど。
久我:ないですねぇ~(笑)。それはもう書けないですね僕は。
──私は人の意見や考えに共感することが滅多にないんですよ。皆無と言ってもいいくらいなんです。今でも他人の意見に「わかる」「私もそう」「それ私の言いたかったこと」ってすぐ同調する人を見ると「怠けてんなぁ」って思っちゃいますし、一時期その嫌悪感が大きくなりすぎて悩んだこともあったくらいで…でも、それとは逆で、共感できないものに感動させられる経験って本当に貴重だと思うんですね。だから、ちょっと好戦的な物言いになりますけど、「自分が同じ経験をしたから」とか「同じことを思っていたから」という理由で覚える感動って、私は音楽の力じゃないと思っているんですよ。
久我:うんうんうん。
──「この曲にはこういう背景があるんです」っていうエピソードを聞いた途端に「めっちゃ泣ける!」って感じで楽曲の評価が上がる様を見ていると「偽物じゃん」って。「もはや音楽である必要すらないじゃん」とまで思ってしまうというか。
久我:なるほどねぇ。
──エピソードでいいなら、それこそメロディーも楽器もいらなくて、ただ隣の人に話せばいいだけのことじゃないですか。あくまでも私個人のなかでのことですけど、やっぱりそういうのって偽物なんですよ。だから、「自分の中にはなかったものに触れて感動する」っていうことに……だからこの「感動」っていうのもちょっと違って……あーんなんて言ったらいいんですかね。あ、例えば映画ひとつとっても、今って「泣けるかどうか」みたいなところあるじゃないですか。
久我:あぁ~はいはい(笑)。そうなってますよね。
──「良い映画=泣ける映画」。あれにもちょっと懐疑的なんですね。私の中で「泣ける」っていう感想は「感動」よりも遥か手前にあるものなんですよ。
久我:はいはいはい。感動より手軽ってことか。
──はい。だから、「自分が感じたことも考えたこともなかったものだけど、すごく好き」とか、「なにがどうなってこうなっているのかは分からないけど、心が震えて止まらない」みたいな、そういう理屈じゃ語れない部分での高揚しか「感動」とは呼びたくないんですね。で、それこそが私にとってのLIPHLICHだったわけです。求められているものを差し出すのではなくて、聴いている人の心にズブッと穴を空けて、作品を出すごとに聴き手自身すら知らなかった新たな嗜好に次々と気付かせて、その穴をどんどん広げていくっていう。
久我:それは嬉しいなぁ!それが一番良い。嬉しいですね。いいなぁ~。
──「LIPHLICHの音楽がドストライク」って言いたくなる気持ちはもちろん私にもあるんですけど、そもそもがそのストライクゾーンとかツボっていうのは元からあったものではなくて、知らぬ間にLIPHLICHに開拓されていたものなんですよね。
久我:いいなぁ~それ。いいですねぇ。
──これを見てくださっている方からすると「お前は何を熱弁してるんだ」って話ですけどね(笑)。でも、私にとってはそういうバンドなんですよ。過去に書いた文章で「LIPHLICHに代演なし」って言葉を使ったんですけど、それは今もずっと思っていることで。ちょっと縁起でもないことを言うようですけど、LIPHLICHがもし解散したとしたら、それは「ひとつのバンドの解散」ではなくて、LIPHLICHを好きな人から「音楽」そのものを消し去ることにもなりかねないと思っているんです。それくらいにLIPHLICHは特殊ですし、知ったからにはずっと観ていたいバンドなので、なくなられるのは本当に困るんですよ。だから、同じ男としても、人にそうまで思わせるものを与えられるアーティストって本当に格好良いなぁって、めちゃくちゃ憧れちゃうんですよね。
久我:うわぁ嬉しいですねぇ。なるほどなぁ。でも、そうかな。そりゃあね、たまにはあるんですよ。「もう嫌だなぁー」ってなることも。でも、そういうときは自分を高めるために「ここで辞めてLIPHLICHがなくなったら、それは音楽界の損失だ」って思うようにしているんで(笑)。
──(笑)きっとその言葉は、ファンの方からしてもすごく嬉しいと思いますよ。好きな音楽がもう生では聴けないってことほど残酷なものはないですから。
久我:それはそうですよね。もちろん亡くなってしまったりとか、そうなってしまうと仕方ないことですけどね。
──やっぱりバンドって夢がありますよ。その形を愛する人からすると、そこへの想いの大きさってとんでもないですから。ただ、そこのボーカルが大好きだからっていっても、じゃあ次に新しいバンドを組んだときに同じだけ好きになれるかっていうと、絶対にそうではないんですよね。
久我:うんうんうん。ないですよねぇ。それはやっぱりそういうもんですよね。
──で、これは私だけかもしれないんですけど、そうそうたるキャリアのあるバンドマン同士が組んでバンドを結成したときに、それを「ひとつの新しいバンド」として認識できなかったりするんですよね。なんかこう…玄人たちの継続セッションバンド…というか…それまでのバンドを好きになったときとは気持ちが大分違うんです。
久我:あぁ~はいはい(笑)。たしかにそれはあるかなぁ。まぁ解散したことがないから分かんないですけどね。他のバンドが解散っていうときも「なんでしたのかな?」って、気持ちが分かんないんですよ。それこそ今は自分で会社を作って、どんどん解散できない、解散するわけにはいかない状況にしているわけですから。なんだろう、やっぱりどこかで意地張ってるんでしょうね。
──その意地は貫いていただきたいです。格好良いですよ。
これはメンバーの皆さんに対して思うことではあるんですけど、その姿を長く見てきたのもあって、久我さんと新井さんには特にずっと一緒にやっていてほしいですね。
久我:そうですね。ずっと一緒にやっていきたいですね。
──元々久我さんってギタリストだったじゃないですか。私、昔から結構強く思っている持論があるんですけど、途中でパートを変えたバンドマンって、自分が元やっていたパートにめちゃくちゃうるさくないですか?
久我:あぁそれはありますねかなり(笑)。
──久我さんは特にそのあたりが強そうだなって思っているんですよ。「俺が認めない奴には絶対弾かせてなるものか」っていう(笑)。やっぱりそういうことを考えても、新井さんへの信頼がすごいんだろうなって嬉しくなるんです。
久我:そうですね。一生一緒にやってほしいですよね。ほら、タッキーはソロインストのアルバムも出すじゃないですか。あれもねぇ、僕もギターやってたんで「自分でも出してみたかったな」ってずっと思っていたんですよ。そういう夢があって。
──それはもう完全に歌なしでってことですか?
久我:あぁー今じゃないですよ?ボーカルを始める前のことです。ギタリストのときは「絶対にギターインストのアルバムを出すんだ!」って、思っていたので。だから、タッキーがそういうアルバムを出すのは、自分のことの様に嬉しいですね(胸に手を当て満面の笑み)。
──新井さんのギター良いですよねぇ。私は、あんまりギターに耳をもっていかれることがないんですけど、どの曲もリフを歌えるくらい新井さんの音が好きなんですよ。なんかこう、感覚的な話になっちゃいますけど、新井さんの出される音って留まらないでずっと移ろいながらとめどなく流れているもの、良い意味で落ち着きがなくて、ずっとそわそわワクワクしているというか、そういうキラッキラな童心を感じるので、バラードであっても聴いていて楽しいんですよ。YouTubeでソロアルバムのSPOTも拝聴したんですけど、LIPHLICHでのドワーンッと外に向かっていく音ではなくて、内に内に入っていくような、内側で鳴っている音を奏でている様な印象を受けましたね。
久我:うん、たしかに。どういう気持ちで作ったのかまでは僕はまだ聞いていないんですけど、やっぱり(バンドのときとは)出る性格が違いますよね。だって、言っちゃえば彼は今ボーカルになっているんですよ。歌詞はないものとしても、ギターで歌っているわけですからね。そういう意味で、より丸裸になっているんですかね。
──改めて自分の感情に素直な方だなって思いました。新井さんのことを知らないという方でも、ギターが好きな方には片っ端から聴いてほしいです。私は入口がLIPHLICHだったので、より一層久我さんのおっしゃる丸裸感を味わっているのかもしれませんね。
久我:うん。ただ、ギターインストになるとやっぱり聴いてもらうための門が狭いじゃないですか。だから、タッキーのキャラを知っている方なら、それを知った上で「じゃあ聴いてみよっかな」って。そうじゃない方でもお気軽にって感じでね。聴いてもらう理由なんてなんでもいいと思うんですよ。
──そうですね。あとこれまた盤で出すっていうのもいいですよね。配信とかじゃなくて。
久我:あぁそれはタッキーのこだわりですね。LIPHLICHは今後盤で出すか分かんないですけど(笑)。でも、そうだなぁ、これからいろいろと楽しくなっていくんだろうなぁ。
──いつか新井さんにもお話を伺う機会があったら嬉しいですね。
久我:お!いいですねぇ。引き出してほしいです新井さんを(笑)。彼はガードが固いですから。
──え?そうなんですか?意外ですね。
久我:ガードっていうか、「自分はこう思っている」っていう部分で模範解答の様な答えを出そうとするときがあるから、もっと引き出してほしいんですよ。
──新井さんは本当に気配りと思いやりの方ですからね。あと、そもそもの性格として、音楽を言葉でどうこう伝えたいと思われるタイプではなさそうですもんね。「言葉で言えないからギターやってんだよ」ってところもあると思うので。
久我:あぁーもうそうそう!だから、逆に好きじゃないというか。言葉、特に文章を書くのが好きじゃないので、話す方が良いんじゃないかな新井さんは。
(なぜ急に新井さん呼びになったのだろう)
──お二人のご予定が合えばになっちゃいますけど、もし宜しければ今回の企画でっていうのはいかがですかね。『SOMETHING WICKED COMES HERE』のリリース当時のことについては久我さんしかお話できないと思うんですけど、新井さんが加入された『LOST ICON’S PRICE』の回でお招きして、当時のことを伺ったりとか…
久我:『LOST ICON’S PRICE』かぁ~二人とも覚えてるかなぁ当時のこと。僕も僕でそのときの気持ちを忘れてしまっていることも多いので、もしかしたら困っちゃうかもしれないですね。言えない様なことならたくさんあるんですけど(笑)。
(私、時計を見て青ざめる)
──…って!ぜんっぜん企画の話してませんでしたね!ごめんなさい!もうこんな時間になっちゃいました。久我さん、あと一時間延長させていただいてもよろしいですか?
久我:あーいえいえ全然。いいじゃないですか。楽しくて。
──じゃあちょっと電話しますので…
(会議室からOKが出る)
──よし!じゃあ始めます!
久我:よし(笑)!
こうしてようやく企画の話へと移るのでした。
企画概要についてお伝えするだけのつもりで久我さんをお呼びしたにも関わらず、この時点で既に一時間半が経過。
さらに言うと、この録音を回す前にも大分話しこんでしまったので(主に私の無駄話)、予定の時間を大幅にオーバーする形となってしまいました。
始めから終わりまでずっと和やかな雰囲気を作ってくださったおかげで、音声上では「(笑)」の表記がない部分も全編にわたって笑い声が残されています。
今回の記事も、久我さんが「せっかく面白いんだからここも回しましょうよ」と言ってくださらなければ存在しなかったものです。なにからなにまで感謝感謝でございます。
がしかしだ。
「いくら優しい方とはいえ、ちょっと甘えすぎたわ…」と帰り道に超反省したので、気を取り直して本編に入る次回からは時間の管理もキッチリ…できるかなぁ…
あ、そうそう。今後こちらのサイトで記事化するものに関しましては私の長すぎる話をかなり簡略化しますのでご安心ください。
今回は音声を公開しないこともあっての全編掲載です。お粗末様でした。
ちなみにYouTubeは規約的にスクショNGですが、こちらのサイトはドメインからなにから私が管理しているので、スクショ大歓迎です。
「久我さんのこの発言良かったな」「ここ面白い!」ってな部分がございましたら、お好きに撮っていただいて、SNS等での投稿にお使いください。
一人でも多くの方の目に留まる様、私も尽力致しますので、「新しいかも」「こりゃ続けてほしいぞよ」と思ってくださった方は拡散にもご協力いただけると大変嬉しいです。
というわけで、【解体新悟】第一審はこれにて閉廷。
長々とお付き合いいただき、有難うございました。次回もお楽しみに。