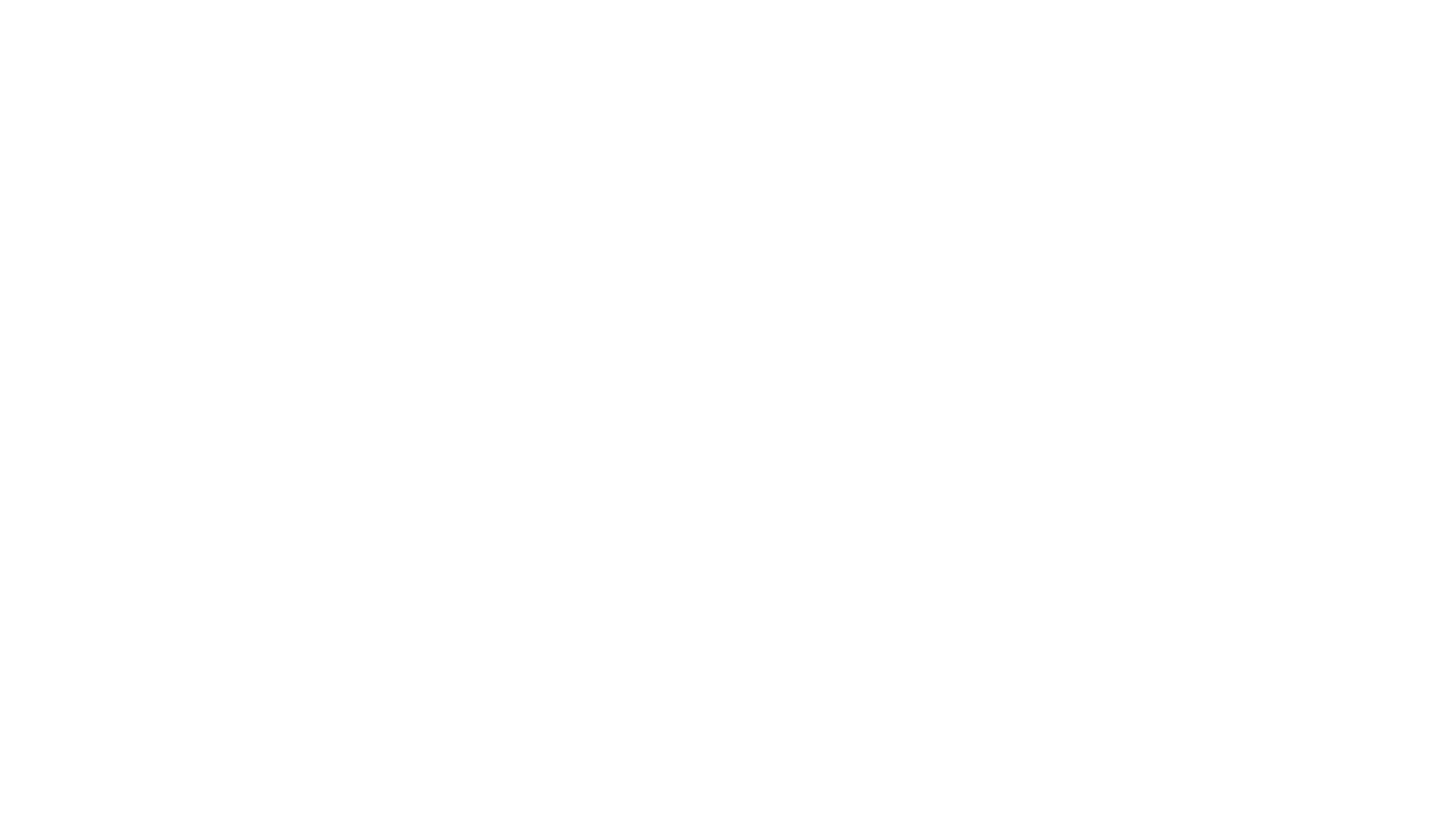小さい頃、どこかへ行くことが好きだった。
場所なんてどこでもよかった。
家から自転車で10分もかからない場所にマルエツがあった。
店内の一画にはパン屋があり、紙のトレイにパンをのせてレジまで持っていくと世にも奇妙な機械で店員さんがパンをトレイごとラップにかけてくれた。
私はその工程を見ているのが楽しくて仕方なかった。パンの味なんてどうでもよかった。
些細な刺激に痺れるようになった私はいつしか「どこでもよかった期」を終えていた。
親に「どこそこ行くけど来る?」と尋ねられたら、決まって「それって遠く?」と聞き返す様になった。
遠くに行くことが好きだった。
そこがどういう場所か、なにが出来るところなのかなんてどうでもよかった。
近所の自販機でジュースを買ってほしくて仕方なかった。
しかし、あまり買ってはもらえなかった。
あたりが出るかどうかを試したかった。ジュースなんてどうでもよ…くはなかった。
夏休みは映画館に行きたかった。
しかし、観たいものなんてドラゴンボールくらいなものだった。
遊園地なんて連れていかれようものなら、心臓が破裂するほど楽しみにしていた。
乗り物は苦手だったけど、そんなことはどうでもよかった。
自分一人じゃ行けないところは総じてワンダーランド。
すべて片道60分以内で着く場所だなんて知らなかった。
私にとって地球は真っ平で、丸ごと一面ニッポンだった。
10歳離れた兄が18で免許を取り、ヤンキー特有の勢いで車を購入した。
小学校低学年の弟にまでそれを自慢したかったのか、毎晩の様に外へ連れ出された。
劇薬レベルの轟音で流れるBUCK-TICKのアルバム『darker than darkness』が耳に痛く、運転席から話しかけてくる兄の声など全く聞こえてこなかった。
曲の善し悪しなんてどうでもよかった。
※ただ当時は『青の世界』の冒頭「青の世界へようこそ(暗黒微笑)」のセリフが怖くて震えていた
小学5年生。ほぼ毎日遊んでいた友達が転校することを知らされた。
彼に限らず、仲良しの子が引っ越すと「もう一生会えない」と思っていた。
転校先がどこか、ここからどのくらい離れた場所なのかなんて知ろうともしなかった。
「知らない」という最高の調味料のおかげで、時間も悲しみも無限だった。
全部が曖昧なくせに、希望と夢ばかりはイヤっちゅうくらい鮮明だった。
二十歳で車を手に入れ、あちらこちらを走り回っていたときにふと気付いた。
「日本って、けっこう狭い」
愉快だけど、なんとなく寂しかった。
ただ、そう思うのは一人で運転をしているときだけで、助手席に友達や恋人を乗せて北へ南へビュンビュンすることにはこの上ない喜びと高揚を覚えた。
左側に座っている人がみんな子供に見えて愛らしかった。
「あの頃の兄ちゃんもこんな気分だったのかな」と思った。
千葉県松戸市常盤平陣屋前にある「ハーモニー八柱」というスーパーダサい名前のアパートで一人暮らしをしていた。
長時間の肉体労働に疲れ果てた体でなんとなくテレビをつけたら、『とんねるずのハンマープライス』という番組がやっており、当時一世を風靡していた大人気アイドルグループが「あなたのためだけに歌う権」なるものを出品していた。
150万円で落札をした男子大学生がとんねるずにマイクを向けられ、ニコニコしながら自己紹介をした瞬間、大袈裟ではなく食べていたピザを皿に落として「ええ!?」と声をもらした。
そこに映っていたのは、5年生の頃に引っ越した例の仲良し君だった。
「千葉の大学に通っている」という言葉に「あぁそういえば船橋に引っ越すって言ってたなぁ」と20年以上前に彼のお母さんから聞いたことを思い出した。
「フナバシなんて聞いたこともない町、さぞかし遠い遠い場所なのだろう」と思っていた当時の自分に「いや、与野(現さいたま市)からでも一時間くらいで着くぞ」と20年越しのつっこみを入れた。
大好きなアイドルに歌詞まで自分の名前に変えてもらって大喜びな様子の彼を横目に「こんな近くにいたのかよ…」と軽口を叩いた。落としたピザのことなんてどうでもよかった。
ショッピングモールへ行けば、幼稚園児がいとも容易く親からジュースを買ってもらい、サーティワンには中学生が列を作っている。
高校生は慣れた手つきでスタバのカップにストローをさし、かと思えば足元では小学生が21時のイオンモールを爆走する。
私の時代では考えられなかったことが当たり前の様に行われていて、それを特別とも思っていない様子の彼らを見ては、「門限のチャイムが鳴り終わる前に帰らねば殺される!」と同級生らと自転車をかっ飛ばしていた頃の自分が大分可哀想な子に思えた。
でも、楽しかったよね。
そんな一言で全嫉妬を丸め込めるくらいには大人になった自分にも気付く。
大切な誰かにポップに怯えていた頃の自分は、なかなかに幸せだったんだということにも。
darknessよりいくらかはdarker thanじゃなかった幼少期。
不安も不満も知らず、暑さ寒さにも苛立たず、不思議と満ちてしまっていた時代が輝かしく思える。
「舞台裏を知りすぎてファンではいられなくなってしまった関係者」
「一途に憧れていた芸能人が犯した罪に失望するファン」
「船橋が隣県であることを知った25歳酒販店店長」
同じ「知らなかった方が族」に所属しながら、私のそれには寂しさをほんのちょっと下回る「よかった」の安堵が共存している。
これすなわち、「しあわせ」というものだろう。
一縷の汚れもない幸せになんて魅力を感じない私にとっては、これくらいの幸がちょうど良い。
「多くを望むこと」
それを未だ知らない私がこの先の未来で「それを望むことの価値」に気付くとき、無欲だった自分を愛おしく思えるかどうか。
それが結構大事なんじゃないかと思っている。
喜怒哀楽のすべてが60%を超え、絶えず器から溢れつづけることで、なにがどれだけ過剰なのかさえ測れずにいる今の自分は死ぬほど滑稽で、笑えないほど卑屈で、誰かを頼りたくて仕方ない。
そんな自分にそろそろ慣れてしまいそうで、それが何よりも怖い。
「そんな頃もあった」と笑える日がくるなら、24倍速でやってきておくれよと願うばかりだ。
あぁいやいや、唐突になんだ。
こんなにもなんでもないぼんやり記事にお付き合いいただき感謝感激雨荒俣宏。
みなさまにおかれましては私の幸を軽ーーーくお祈りいただきつつ、引き続き素敵なサンデーをお過ごしくだpsychedelic modulation(フー⤴︎)